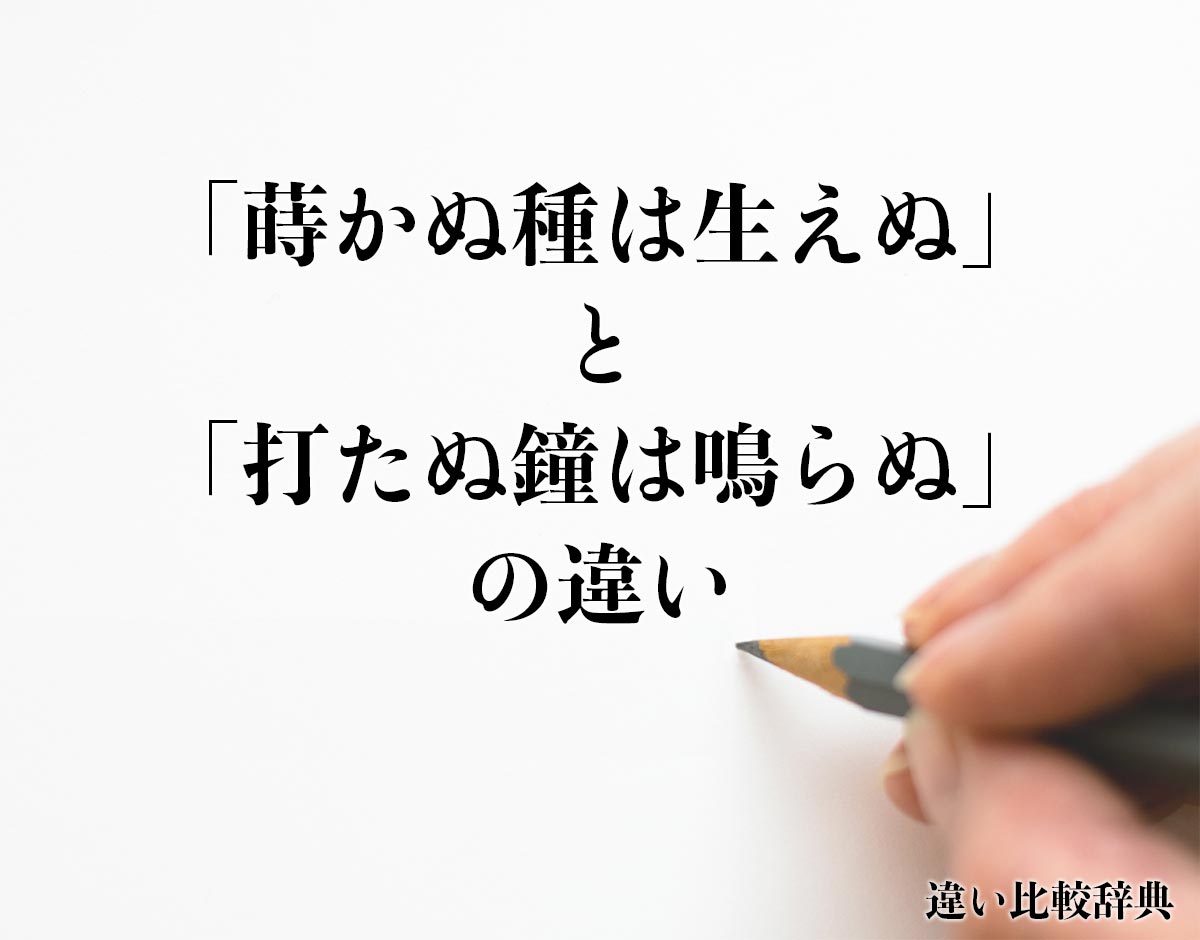この記事では、「蒔かぬ種は生えぬ」と「打たぬ鐘は鳴らぬ」の違いを分かりやすく説明していきます。
「蒔かぬ種は生えぬ」とは?
問題が起きるのは、何かしらの原因があるからという意味がある言葉を「蒔かぬ種は生えぬ」【まかぬたねははえぬ】です。
このような意味から、行動しなければ自分にとっていい結果はならないと例えられます。
それほど自ら行動するということには重要な意味があり、やがて大きな実となり、花になるのです。
良い結果を得たいなら、率先仕事するのが大事という意味合いで使われています。
「打たぬ鐘は鳴らぬ」とは?
何かしらの原因が生じては、結果につながるという意味で使われている言葉が「打たぬ鐘は鳴らぬ」【うたぬかねはならぬ】といいます。
このようなところから、行動しなければ効果は得られないといった意味になるのです。
とにかく迷っては立ち止まっていないで、興味があれば実行に移す行動が大事であり、苦労したり、頑張って努力するのが成果につながるといった意味があります。
「蒔かぬ種は生えぬ」と「打たぬ鐘は鳴らぬ」の違い
「蒔かぬ種は生えぬ」と「打たぬ鐘は鳴らぬ」の違いを、分かりやすく解説します。
種は地面に蒔かなければ苗が生えてこないというように、結果を得たいのなら自ら行動しないと成果さえ得られないという意味になります。
もう一方の「打たぬ鐘は鳴らぬ」は自ら挑戦したり、実行に移さなければ成果は得られないといった意味合いがある言葉です。
良い成果を得たいなら、それなりに努力しなければ良い結果にはならないので、行動するのが大事ということわざになります。
「蒔かぬ種は生えぬ」の例文
・『蒔かぬ種は生えぬと、面倒な作業を請け負えば信用につながった』
・『自分を変えようと、蒔かぬ種は生えぬを胸に仕事するようにした』
「打たぬ鐘は鳴らぬ」の例文
・『仕事するとき、打たぬ鐘は鳴らぬと頑張れば上司に褒められた』
・『打たぬ鐘は鳴らぬと思い、国家試験を受けると合格した』
まとめ
意味としては似ていることわざではありますが、少し使い方が異なります。
どういった場面で使えばより言葉になるかうまく活かせるかを考えてみましょう。