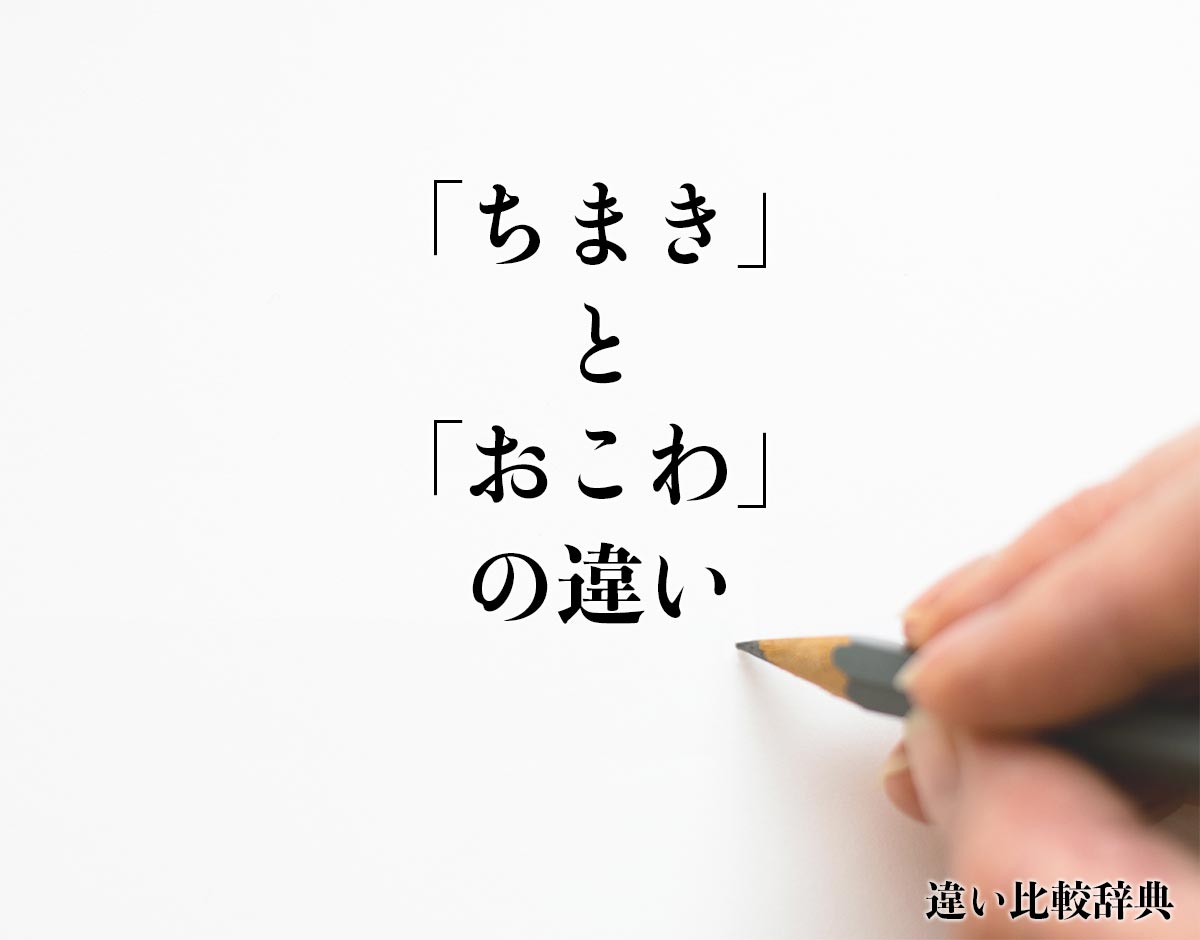この記事では、「ちまき」と「おこわ」の違いを分かりやすく説明していきます。
「ちまき」とは?
うるち米、もち米、米粉などで作った餅、あるいはもち米を三角形や円錐形に整え、ササや葦の葉で包み、イグサなどで縛って蒸した食べもののことです。
中国から伝わってきた食べものです。
特に端午の節句のときによく食べられています。
材料は米です。
米にはうるち米ともち米がありますが、どちらもこの料理に使われています。
米と一緒に野菜やシイタケなどを混ぜたり、醤油などで味付けをすることもあります。
使用する葉は、ササ、葦、チガヤ、竹などさまざまです。
三角形や円錐形に形を整えて葉で包みます。
葉を縛るものは、イグサやタコ糸などです。
作り方を簡単に説明します。
もち米は洗って水を切り、ざるにあげておきます。
にんじん、たけのこ、豚肉、戻した干ししいたけを切ります。
鍋に油をひいて豚肉を炒め、そこにたけのこ、にんじん、しいたけを加えて炒めます。
醤油、酒、砂糖を混ぜ合わせたものを加え、汁が半分くらいになるまで煮詰めます。
洗っておいたもち米を別の鍋で炒め、透き通ってきたら先ほどの野菜などを加えて混ぜます。
これをいくつかに分けて、ササなどの葉に包み、タコ糸などで縛ります。
これを蒸し器で蒸したら完成です。
葉を巻くときにすき間がないようにきっちりと行うようにします。
こうするとうまく蒸しあがり、もっちりとした食感になります。
この食品は中華料理店で食べることができ、また端午の節句近くになるとスーパーで売られることもあります。
「ちまき」の言葉の使い方
もち米やうるち米をササなどの葉で包んで蒸した食べものを指して使用する言葉です。
「おこわ」とは?
もち米に小豆以外の材料を加えて炊いた食べもののことです。
米にはもち米とうるち米があり、食感が異なります。
もち米はもちもちとした食感で、それに比べるとうるち米はさっぱりした食感です。
この違いは、米に含まれるアミロースとアミロペクチンの割合の違いによるものです。
もち米の方がアミロペクチンを多く含んでおり、ねばりがあり、もちもちとした食感になります。
この言葉が指す食べものは、ただもち米を炊いたものではなく、他の材料を混ぜ合わせます。
混ぜ合わせるものは、栗、山菜、きのこ、鮭、鶏肉など、小豆以外のものです。
醤油で味付けをすることもあり、こげができてそこがおいしいという人もいます。
「おこわ」の言葉の使い方
もち米に栗や山菜など小豆以外のものを加えて炊いた食べものを指して使用する言葉です。
小豆を使っている場合は赤飯といいます。
「ちまき」と「おこわ」の違い
もち米を使っている点が似ていますが、別の食べものです。
前者はササや葦などの葉で包んで蒸しています。
後者はササの葉などで包むことはなく、炊いて調理をします。
まとめ
もち米を使った食べものという点が似ていますが、葉で包むのか、包まないのか、蒸すのか、炊くのかという点に違いがあります。