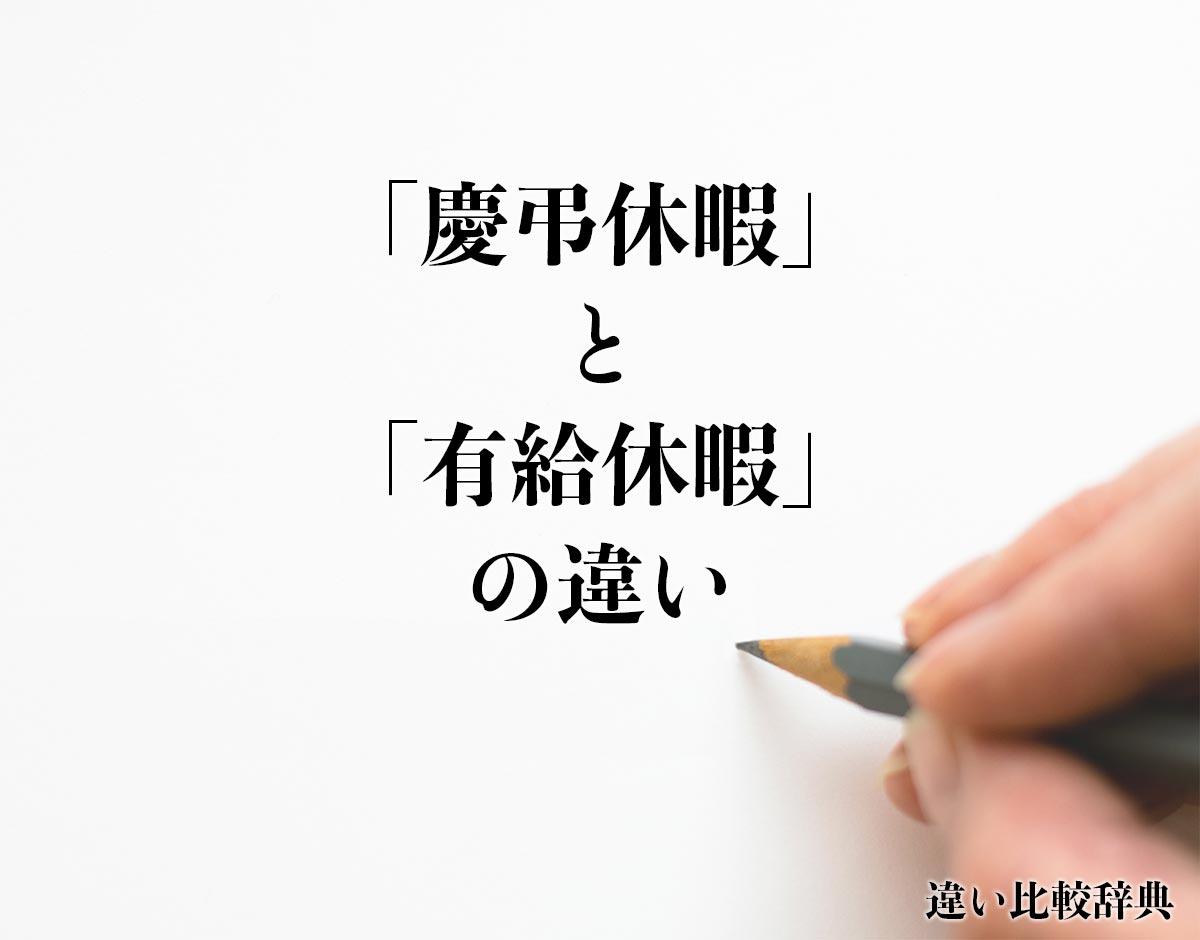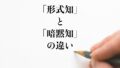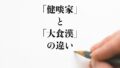この記事では、「慶弔休暇」と「有給休暇」の違いを分かりやすく説明していきます。
「慶弔休暇」とは?
結婚、出産、葬儀などの理由で取得できる休暇のことです。
慶弔には、結婚や出産などの祝うこと、死などの悲しむことという意味があります。
結婚は一生の中で何度もあるものではありません。
好きな人と一緒になれることはめでたいことといえるでしょう。
新しい命が誕生することもめでたいことです。
人が死を迎えたら、もうその人の肉体を目にすることはできません。
これは悲しいことといえるでしょう。
休暇とは、会社などで定められた休みのことです。
土・日・祝日などではない休みを指しています。
結婚や葬儀などによる休みは、会社が定めている場合もあれば、定めていない場合もあります。
定めている場合なら、休んでも賃金が支払われます。
しかし、定めていない場合は会社によって対応が違い、賃金が支払われないことがあります。
また、何日休めるのかも会社によって異なります。
本人が結婚をする場合だと3~5日、子どもが結婚をしたときは2日程度など、誰が結婚したかによって休める日数が異なります。
配偶者が亡くなったときには10日ほど、兄弟姉妹や孫など2親等にあたるものが亡くなったときには2~3日程度です。
誰が亡くなったかによって休める日数が異なります。
この言葉が指すものを取得するには、事前に会社に伝えておく必要があります。
葬儀の場合は難しいですが、結婚式などは日程がわかっているので、直前になってから伝えるのではなく、早めに伝えるようにします。
「慶弔休暇」の言葉の使い方
結婚や葬儀などの理由で取得する休みを指して使用をします。
風邪など体調不良による休みのことではありません。
「有給休暇」とは?
会社を休んでも給料をもらえる休みのことです。
仕事をしないと給料はもらえません。
しかし、この言葉が指すものは仕事を休んでも給料が発生をします。
この休みは法律で定められており、働く者に与えられています。
契約社員とパートやアルバイトでは、1年間にもらえる日数が異なります。
まとまった休みをとってリフレッシュする人もいれば、病気などの理由で休まなければならないときに、この休暇を使う人もいます。
休みの日に何をするかは人それぞれです。
だらだら過ごす、掃除をする、旅行をする、起床をする、読書をするなどして過ごしている人もいるようです。
「有給休暇」の言葉の使い方
休んでも給料をもらえる休暇を指して使用する言葉です。
土・日・祝日の休みとは異なります。
「慶弔休暇」と「有給休暇」の違い
前者は、喜ばしいことや悲しいことがあったときの休暇です。
会社によって定めているところと、定めていないところがあります。
後者は休んでも給料が発生する休暇のことです。
何の理由で休むかは意味に含まれていません。
どの会社でも定めています。
まとめ
何の理由の休暇なのか、給料が発生するのかに違いがあります。