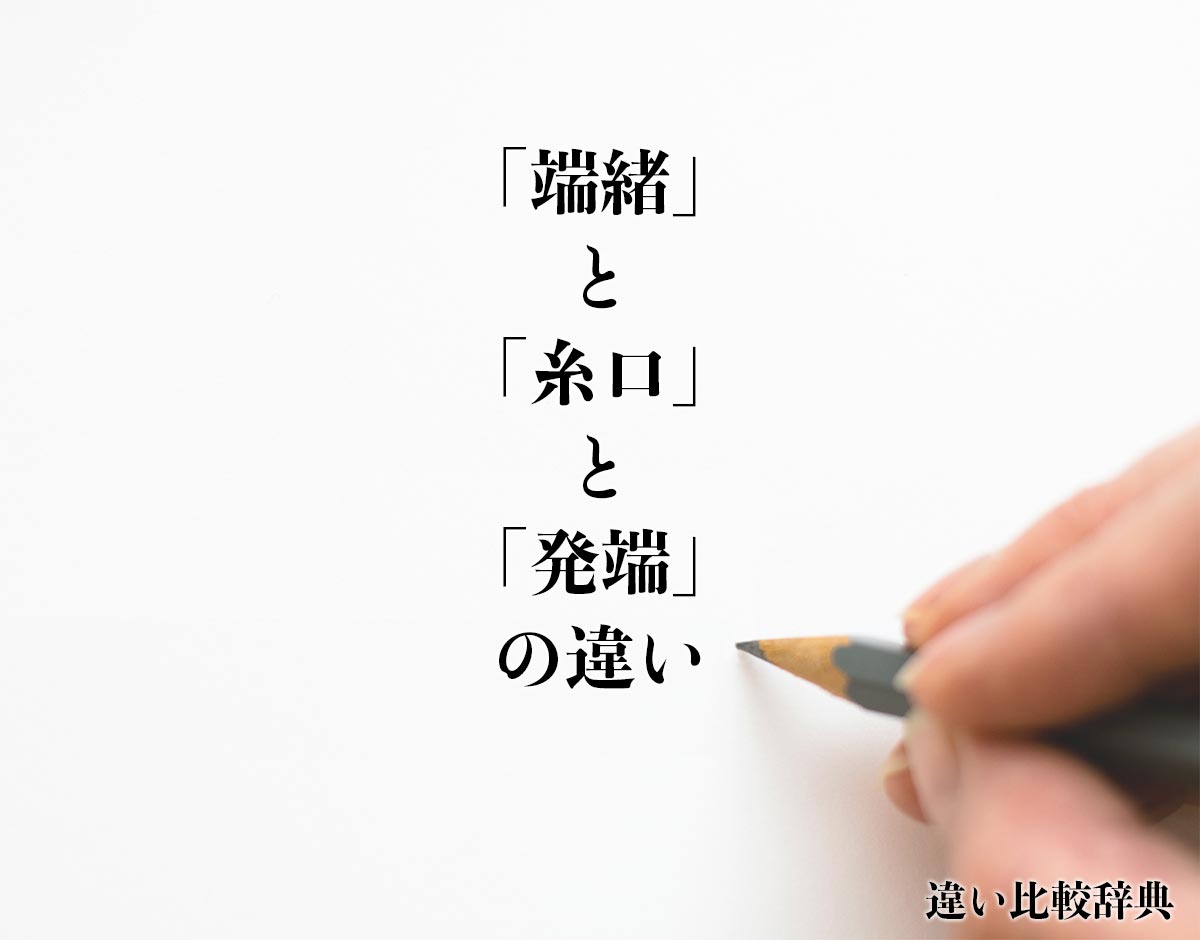この記事では、「端緒」と「糸口」と「発端」の違いを分かりやすく説明していきます。
「端緒」とは?
「端緒」は「たんしょ」と読みますが「たんちょ」と読むこともあります。
「端緒」には「物事の始まり。
糸口。
手がかり」という意味があります。
例えば、何かが発展していくためには、その始まりとなるものがあるはずです。
そのような手掛かりとなるものを「端緒」と呼びます。
「端緒」の言葉の使い方
例えば、ある国の文化が世界的に評価されるとき、そのきっかけとなる映画やアート作品、イベントなどがあるのではないでしょうか。
例えばある映画が文化を広めるきっかけになったとしたら、「あの映画が、文化を世界に広める端緒を開いた」などという文章にできます。
「糸口」とは?
「糸口」は「いとぐち」と読みます。
「糸口」は、「巻いてある糸の端。
糸の先」という意味があります。
次に「糸口」には、「きっかけや手がかり」という意味があります。
巻いている糸の端を見つけることができれば、糸全体を手に入れることができます。
同じように、何かのきっかけや手がかりとなるものを「糸口」と言います。
「糸口」の言葉の使い方
例えば、殺人事件が起こった時、犯人が誰なのか警察が捜査を行います。
道に落ちていた、凶器が発見されたとき、この凶器が犯人特定の手がかりになるかもしれません。
このような場面で、「犯人特定の糸口となる、凶器を発見した」などという文章を作ることができます。
「発端」とは
「発端」は「ほったん」と読みます。
「発端」には「物事の始まり。
事の起こり」という意味があります。
大きな出来事が起こる時、その始まりとなる出来事があるはずです。
このような始まりの何かを「発端」と呼びます。
「発端」の言葉の使い方
第一次世界大戦は、たくさんの国と兵士を巻き込んだ、かつてない大きな戦争となりました。
しかし、その始まりは、ある国の皇太子が暗殺されたことに始まると言います。
この場合は、「ある国の皇太子が暗殺されたことが、第一次世界大戦の発端だった」という文章を作ることができます。
「端緒」と「糸口」と「発端」の違い
「端緒」には「物事の始まり。
糸口。
手がかり」という意味があります。
次に「糸口」には、「きっかけや手がかり」という意味があります。
さらに「発端」には「物事の始まり。
事の起こり」という意味があります。
「端緒」と「糸口」は、物事を始めたり、解決するときに手がかりになるものを意味する言葉となり、同じ意味を持つ同義語となります。
一方で、「発端」は、物事の始まり、始まることを意味します。
このように、「端緒」と「糸口」は、「手がかり」という意味を持つのに対して、「発端」は手がかりという意味は持たず、単純に、何かの始まり、何かが始まったことを意味するという違いがあります。
まとめ
「端緒」と「糸口」と「発端」の違いについて見てきました。
3つの言葉の違いを知り、使い分けられるようにしましょう。