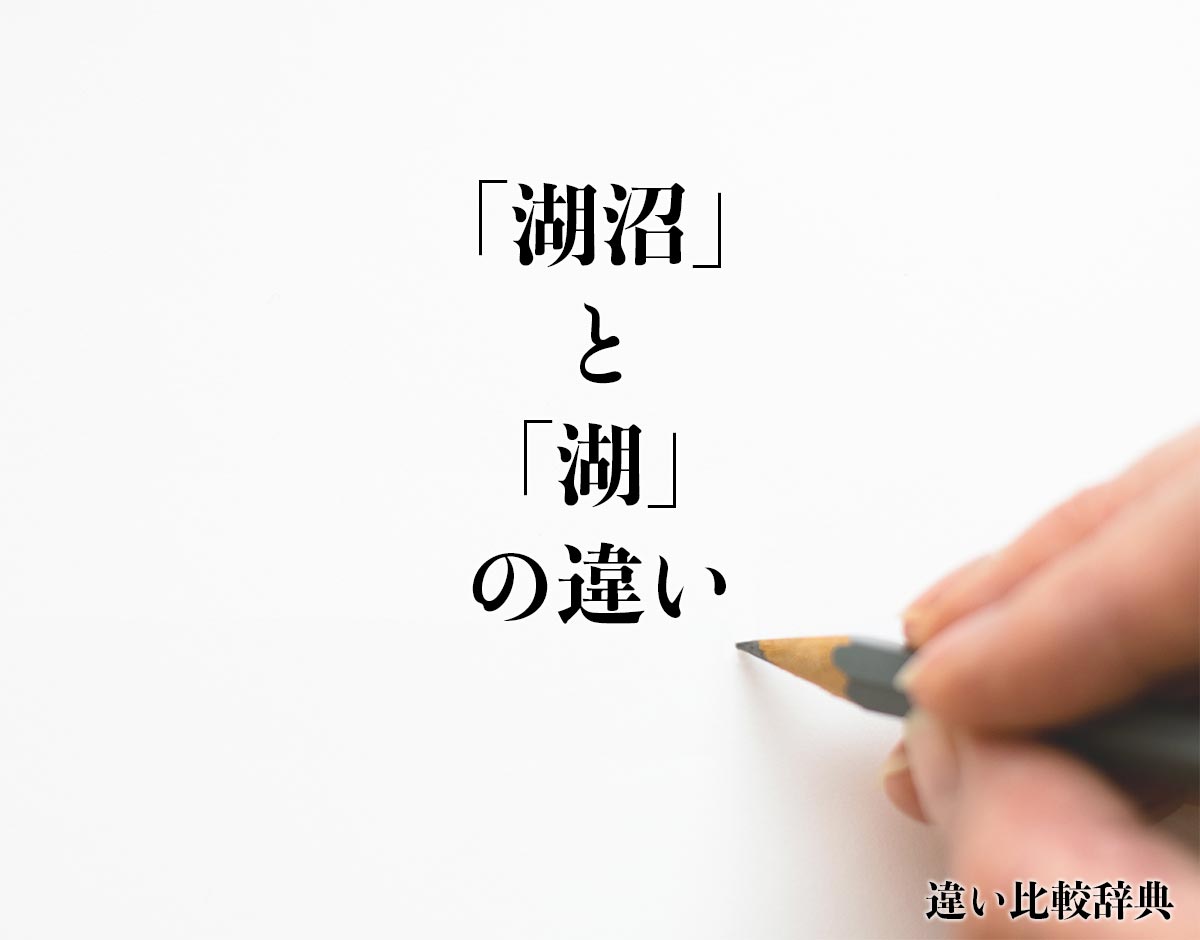この記事では、「湖沼」と「湖」の意味や違いを分かりやすく説明していきます。
「湖沼」とは?
周囲を陸に囲まれている窪んだ水域を「湖沼」【こしょう】といいます。
周りに海があるわけでもないのに雨が降って溜まったり、川の水が入り込んで出来た湖のようにも見える窪地を指すのです。
沼よりも面積が広く、中には人間が水を入れた「人工湖沼」があります。
このように、四方を陸になっているその中心に貯留する水域を指すのです。
「湖」とは?
水海と呼ばれていた「湖」【みずうみ】の水深は5m以上と深く、窪みにできた水域を指します。
淡水の「湖」は淡海といい、琵琶湖を指すのです。
また、塩が含まれている湖を「塩湖」【えんこ】と呼び、塩がとれるため人々の暮らしを潤します。
世界にはカスピ海やビクトリア湖といった面積が広い所もあり、多くの観光客を惹きつけるのです。
日本では鹿児島県の池田湖が選ばれていて、福島県の猪苗代湖は磐梯山との美しい光景が観光客を呼びます。
「湖沼」と「湖」の違い
ここでは「湖沼」と「湖」の違いを、分かりやすく解説します。
前後左右すべて陸になっていて、海から海水が流れてこない水域を指します。
窪地であるため雨や少量の川の水が入り込み、湖のように見える水域となるのです。
もう一方の「湖」は陸地に囲まれていて、沿岸植物が生えず、底までの深さがある水域を指します。
深さとしては5m以上の水深がある窪みにできた水域で、遊覧船に乗って景色を楽しめる場所でもあり、観光客を楽しませる観光地となるのです。
「湖沼」の例文
・『海からの生き物はいない湖沼の生態系は独立している』
・『湖沼を守るため環境税を徴収するのが茨城県だ』
「湖」の例文
・『マリモが生息する阿寒湖は神秘的な美しさが魅力だ』
・『塩分濃度が高く、広かったアラル海の面積が小さくなった』
まとめ
「湖」を使った水域を指しますが、水深や規模に違いが見られます。
どういった水域を指すかに注目して、比較するといいでしょう。