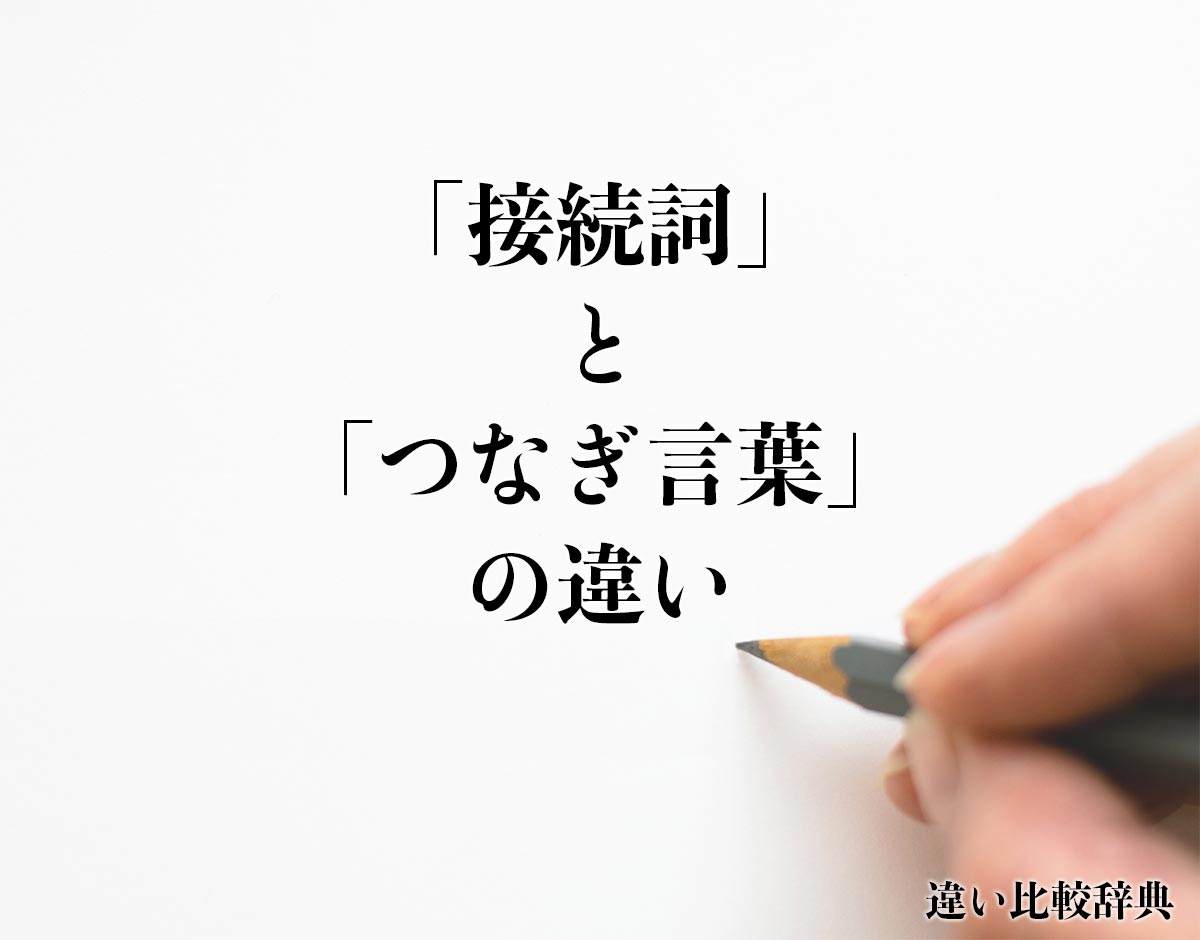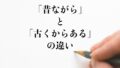この記事では、「接続詞」と「つなぎ言葉」の違いを分かりやすく説明していきます。
「接続詞」とは?
品詞の一種で、文と文、または語句と語句をつなぐ自立語のことです。
自立語とは、単独で意味を持ち、文節の頭に来る語のことです。
接続詞は活用しないので、形は変わりません。
接続詞の例としては、「しかし」「また」「それとも」などがあります。
また、接続詞は、前後の文や語句の関係性を表します。
「つなぎ言葉」とは?
文法用語ではなく、文章の作成技法の一つです。
文と文をつなぐ言葉のことを指します。
つなぎ言葉には、接続詞だけでなく、接続助詞や用言の連用形なども含まれます。
接続助詞とは、助詞の一種で、文と文をつなぐ付属語のことです。
付属語とは、自立語に付いてその意味や形を変える語のことです。
接続助詞の例としては、「ので」「から」「けれど」「ながら」などがあります。
「接続詞」と「つなぎ言葉」の違い
「接続詞」と「つなぎ言葉」の違いを、分かりやすく解説します。
「接続詞」は品詞の一つで、自立語として文や語句をつなぐものです。
その一方で、「つなぎ言葉」は文章の作成技法で、接続詞以外にも接続助詞や用言の連用形などを含む、文と文をつなぐ言葉の総称です。
この違いを理解することで、日本語の文章の構造や表現について、より深く理解できることでしょう。
「接続詞」の例文
・『彼の文章には接続詞がないので、文脈がめちゃくちゃだ』
・『どんな言語でも、接続詞がないと、きちんとした文章にはならない』
「つなぎ言葉」の例文
・『彼はつなぎ言葉として、とにかく「つまり」という言葉を多用する』
・『つなぎ言葉を使用することによって、文章にメリハリをつけることが可能だ』
まとめ
「接続詞」と「つなぎ言葉」は、文と文をつなぐ言葉のことです。
接続詞は品詞の一種で、「しかし」「また」などがあります。
その一方で、つなぎ言葉は、接続詞以外にも副詞や助詞などが含まれます。
「たとえば」「つまり」「なぜなら」などがあります。
それぞれの言葉を正しく使い分けられるように注意しましょう。