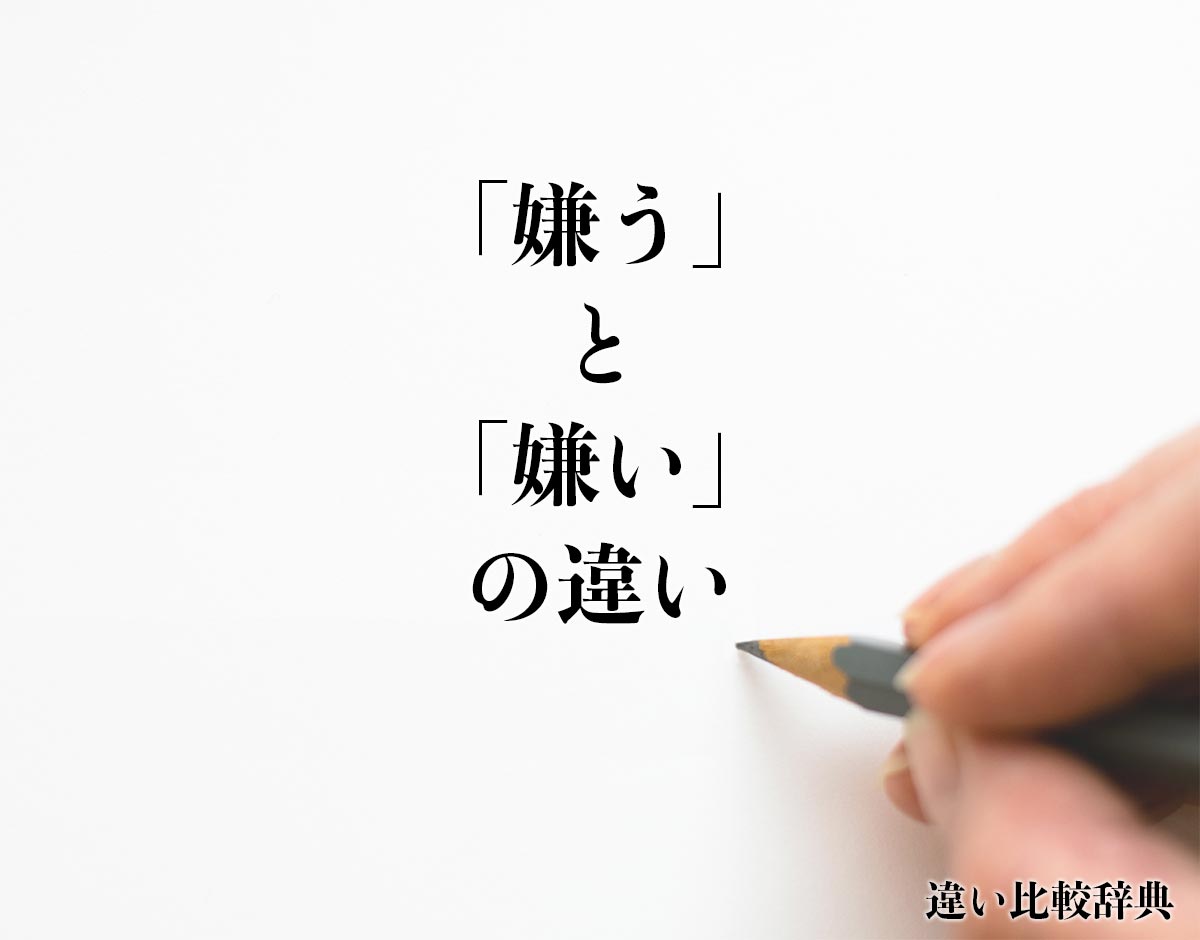この記事では、「嫌う」と「嫌い」の違いを分かりやすく説明していきます。
「嫌う」とは?
この言葉の主な意味は3つあります。
1つめは、嫌がってそのものとのかかわりを避けたいと思う、好ましくないとして避けるという意味です。
たとえば、会うたびに愚痴をいう人がいるとします。
愚痴をいわれてよい気分にはなりません。
自分はこの人のことを好ましく思っておらず、避けたい人と考えています。
このことを「愚痴をいう人を嫌う」といいます。
2つめは、そうすることを不愉快だと思う、遠慮してそれをしないようにするという意味です。
葬式は友引の日にしない方がよいとされています。
このことを「葬式は友引の日を嫌う」といいます。
3つめは、それがあると傷つくなどするので避けるべきであるのです。
塩は湿気の多いところに置いておくと、べたついてしまいます。
これでは調理の際に使いにくいので、湿気があるところに置くのは避けるべきです。
これを「塩は湿気を嫌う」といいます。
「嫌い」とは?
この言葉の意味は主に3つあります。
1つめは、嫌だと思うこと、またそのさまです。
たとえば、ピーマンを食べるのを嫌だと思っているとします。
これを「ピーマンが嫌い」といいます。
2つめは、「きらいがある」という使い方をして、好ましくない傾向という意味です。
「真面目過ぎるきらいがある」のような使い方をします。
3つめは、「〜ぎらい」の形で使って、その物事をするのが嫌であることという意味です。
「勉強嫌い」のような使い方をします。
「嫌う」と「嫌い」の違い
「嫌う」と「嫌い」の違いを、分かりやすく解説します。
前者は動詞、後者は名詞という違いがあります。
また、前者にはそれをしないようにする、傷つくなどするので避けるべきであるという意味がありますが、この意味は後者にはありません。
後者は「きらいがある」「〜ぎらい」の形で使われることもあります。
まとめ
動詞なのか、名詞なのかという違いがあります。