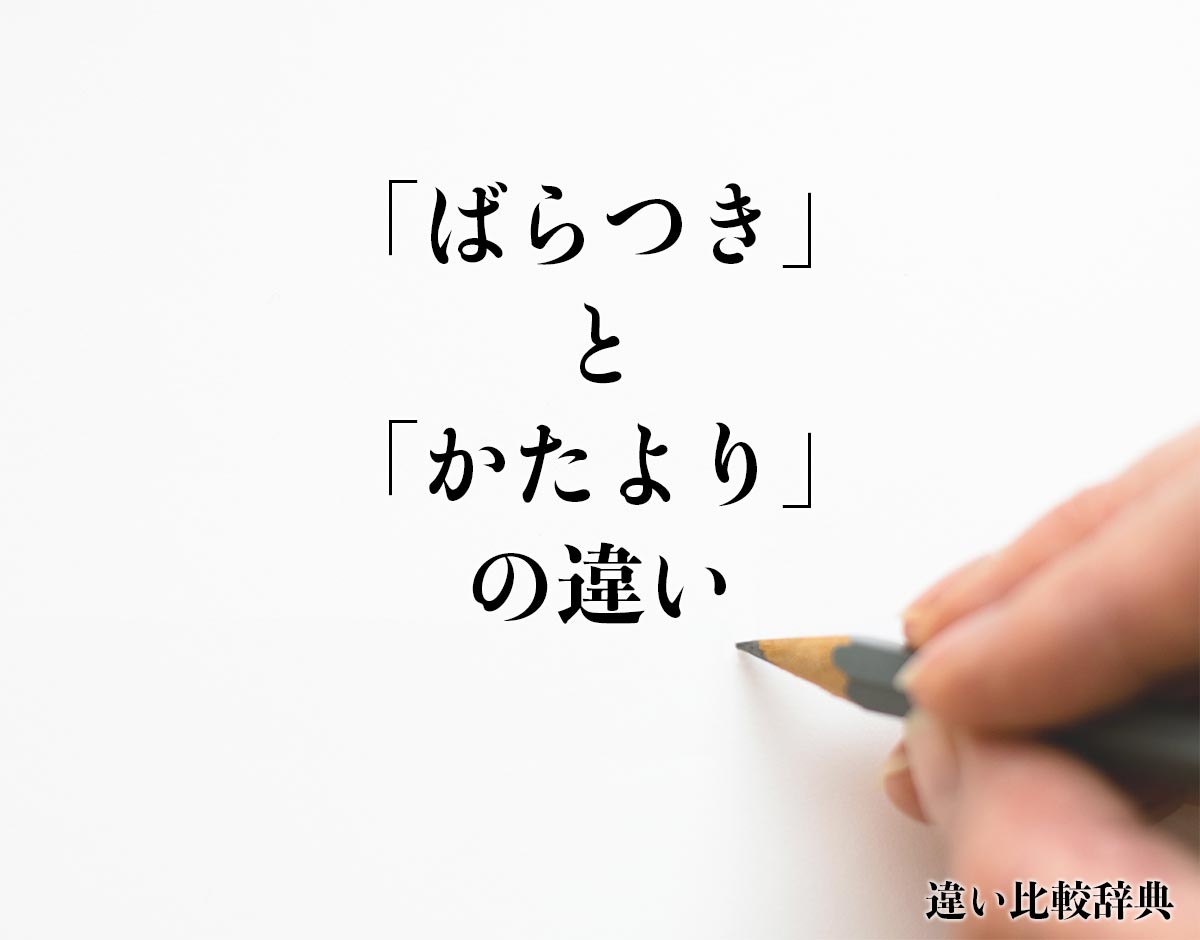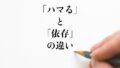この記事では、「ばらつき」と「かたより」の違いを分かりやすく説明していきます。
「ばらつき」とは?
すべてが同じなのではないこと、ふぞろいであることという意味です。
たとえば、パスタの上にタバスコを振りかけたとします。
パスタとタバスコを混ぜなければ、辛い部分とそうでない部分ができます。
味が均一ではないのです。
このことを「味にばらつきがでる」といいます。
家庭菜園でトマトを育てたとします。
収穫できたものは、大きなものもあれば、小さなものもありました。
これは「多きさにばらつきがある」といいます。
また、測定した数値などが不規則に存在することという意味もあります。
「かたより」とは?
ある部分や方向に集まっていて、全体のつり合いが取れていない状態という意味です。
三大栄養素とは、炭水化物(糖質)・脂質・タンパク質のことです。
そうめんばかり食べていると、炭水化物ばかりを摂ることになり、脂質とタンパク質は不足し、栄養素の全体的なつり合いが取れていない状態になります。
これを「栄養素にかたよりがある」といいます。
取り扱いや考え方が公正・公平ではないという意味もあります。
ある母親は、上の子のことはかわいがっているけれど、下の子のことはあまり構っていなかったとします。
こういった平等ではないさまをいいます。
「ばらつき」と「かたより」の違い
「ばらつき」と「かたより」の違いを、分かりやすく解説します。
均一でないという意味が似ていますが、それぞれの意味は異なります。
後者は一方に寄ることです。
ある部分や方面に集中をして、つり合いが取れていない状態であることをいいます。
前者は一方に寄っているのではありません。
たとえば、ハンバーグの右側だけがしょっぱくて、左側はおいしい味だとします。
これは後者の意味です。
ハンバーグにしょっぱい部分もあれば、そうでない部分もあるとします。
どこか一部分にだけしょっぱさが寄っているのではないけれど、味が均一ではありません。
これは前者の意味です。
まとめ
一方はふぞろいであること、もう一方はある部分や方向に集中をしてつり合いが取れていないことで、2つの言葉の意味は異なります。