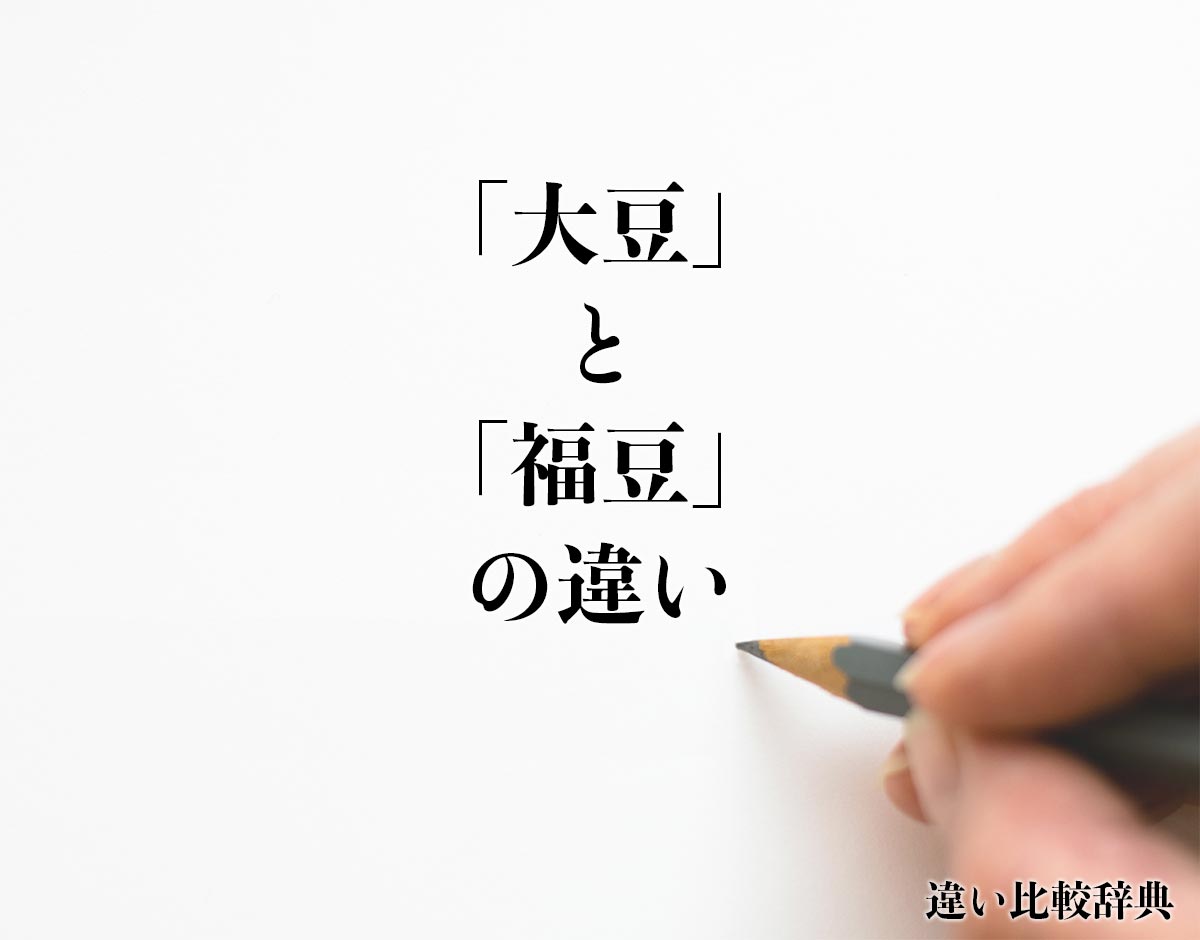この記事では、「大豆」と「福豆」の違いを分かりやすく説明していきます。
「大豆」とは?
大豆とはマメ科の一年草で、農作物として古くから栽培されてきました。
世界中で栽培されていますが、日本でも縄文時代にはすでに存在していたといわれています。
種子を食用としており、油の原料にもなります。
油を搾った後の粕も家畜の飼料として用いられてきました。
大豆にはタンパク質が豊富に含まれることから畑の肉と呼ばれることもあります。
大豆は様々な食品に加工されており、豆腐や納豆、油揚げ、味噌、醤油、きな粉など色々あります。
近年は、大豆ミートなど代替肉として用いられることもあります。
宗教上の理由で肉が食べられない人や菜食主義の人等から人気を集めています。
また、ダイエットや健康を目的に大豆ミートを食べる人もいます。
それから大豆はバイオマス燃料などに加工されることもあり、工業用にも使われています。
「福豆」とは?
福豆とは、節分の豆まきの時にまく大豆のことをいいます。
炒った大豆を使うことが多く、「鬼は外、福は内」と声をかけながらまきます。
節分は現在2月3日を指しますが、元々は立春・立夏・立秋・立冬の前日のことを指していました。
立春の前日にあたるのが2月3日なのです。
季節の変わり目には邪気が生じ鬼が出るといわれていたので、それを払う目的で豆をまくようになりました。
豆などの穀物には邪気を払う力があると信じられていたのです。
炒った大豆をまくことで邪気を払い、福を呼び込むことから福豆と呼ぶようになりました。
福豆を入れる枡は、福枡と呼ばれています。
「大豆」と「福豆」の違い
福豆は節分の時にまく大豆のことを指しているので、大豆と福豆は同じものです。
大豆は様々な食べ物の原料になっており、その際には大豆と呼んでいます。
福豆と呼ぶのは節分の時に限られます。
まとめ
節分の時にまく大豆が福豆です。
節分以外の時に福豆と呼ぶことはありません。