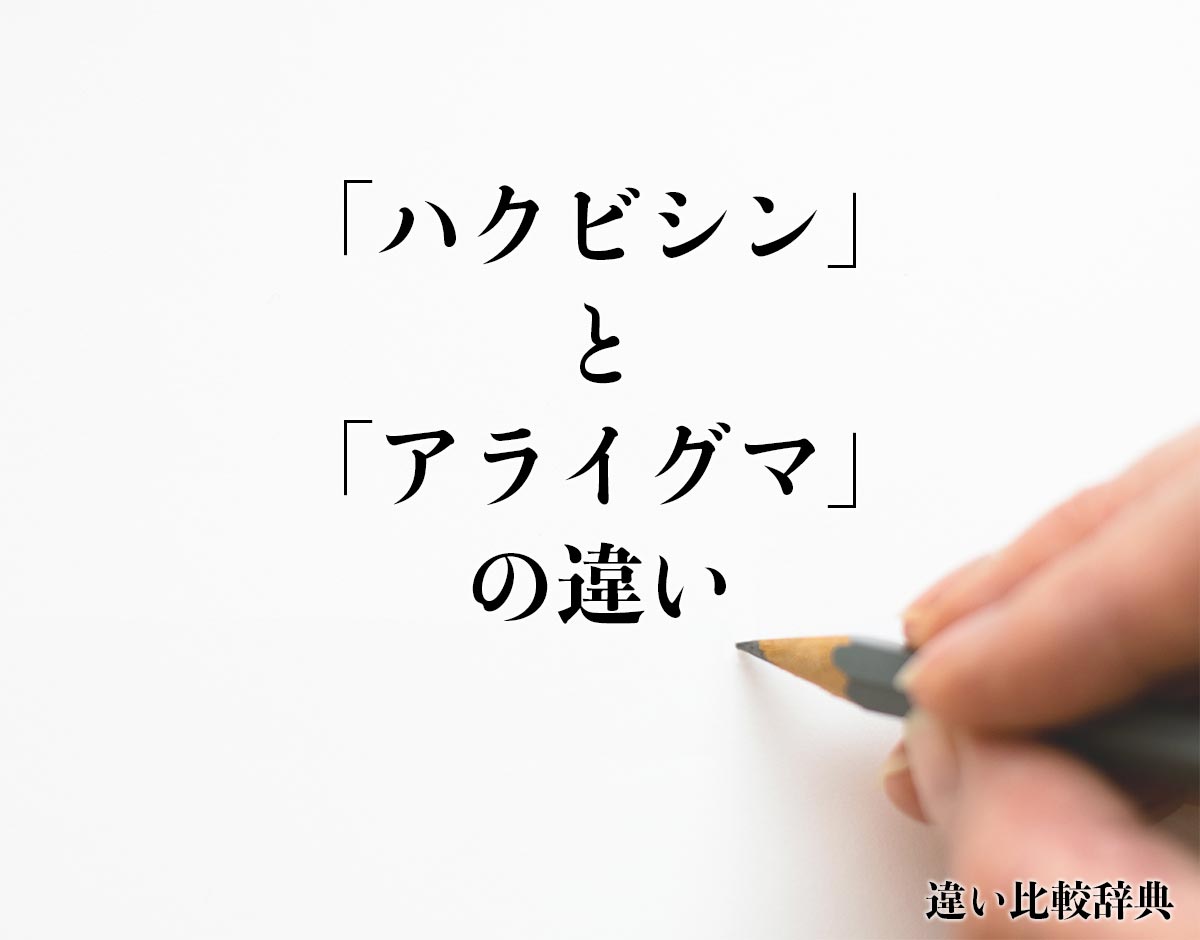この記事では、「ハクビシン」と「アライグマ」の違いを分かりやすく説明します。
「ハクビシン」とは?
ハクビシンとは、ジャコウネコ科ハクビシン属に属する動物です。
アジアに分布していて、日本にも本州から九州にかけて生息しています。
外来種と考えられていますが、日本に流入した時期などはよく分かっていません。
ハクビシンを漢字で書くと「白鼻芯」となります。
名前の通り鼻筋に白い線があり、体長は50cmから75㎝程です。
ハクビシンは雑食性で、果実や野菜、昆虫、ネズミなどを食べます。
果樹園や畑で農作物を食い荒らされる被害も出ています。
「アライグマ」とは?
アライグマとは、アライグマ科アライグマ属に属する動物です。
北アメリカが原産で、アメリカやカナダ、メキシコなどに自然分布しています。
日本には1970年代にペットとして飼われるようになり、それが野生化して各地で繁殖しました。
見た目は可愛らしいですが、気性が荒いのでペットにはあまり向きません。
目を覆うように黒い帯があるのが特徴で、夜行性です。
日本ではアライグマによる農作物の被害も出ており、特定外来生物に指定されています。
「ハクビシン」と「アライグマ」の違い
ハクビシンとアライグマは見た目が似ていますが、違う種類の動物です。
ハクビシンは鼻に白い線があるのが特徴で、アライグマは目に黒い帯があるのが特徴になります。
どちらも空き家などの家屋に棲みついたり、農作物を食い荒らすといった被害をもたらします。
ただし、特定外来生物に指定されているのはアライグマだけです。
特定外来生物は、明治以降に日本に流入した動物が対象となります。
ハクビシンは外来種ですが、それよりも前に日本に流入したと考えられています。
まとめ
ハクビシンは顔に白い線がありますが、アライグマは目に黒い帯があります。
それから特定外来生物に指定されていて、駆除対象となるのはアライグマの方です。