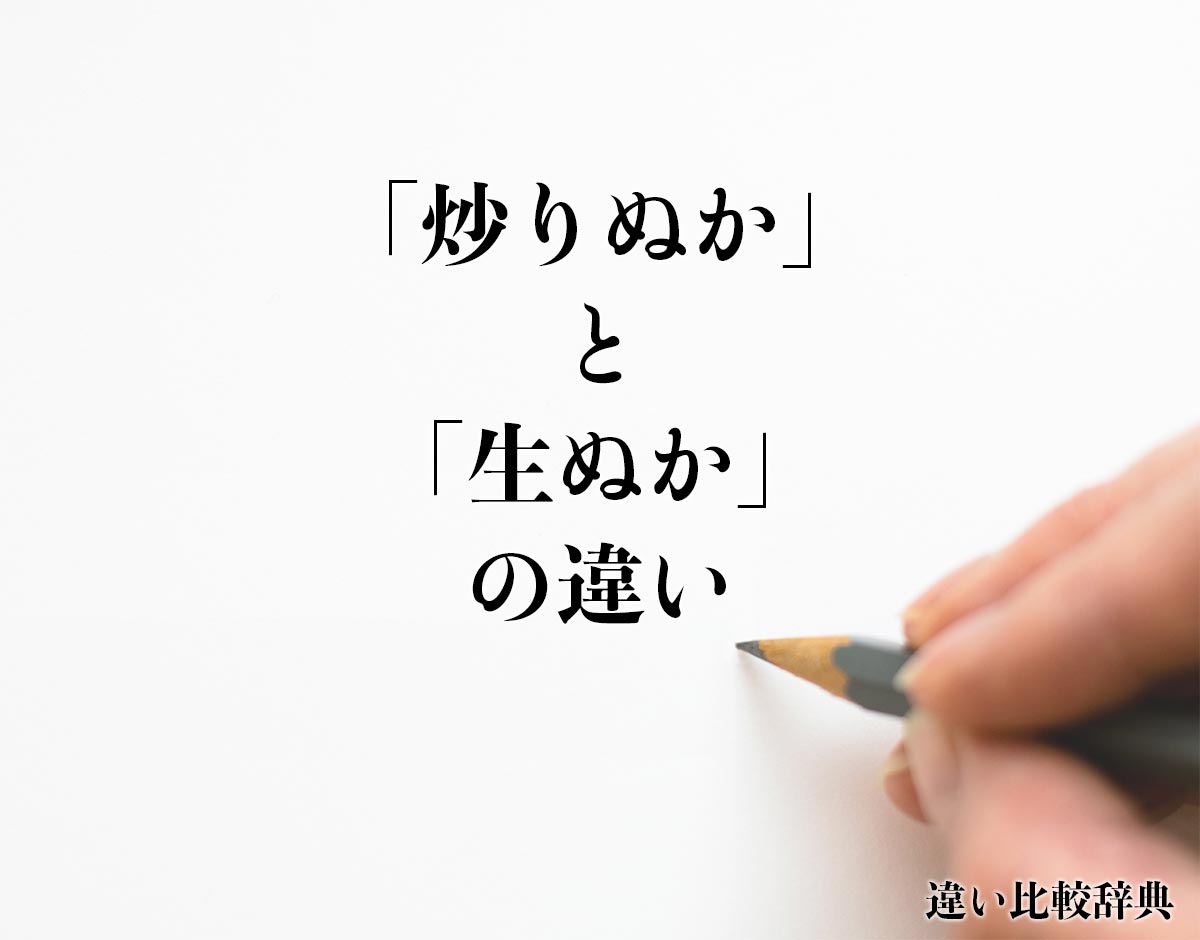この記事では「炒りぬか」と「生ぬか」の違いについて紹介します。
炒りぬかとは?
炒りぬかとは、米ぬかを炒ったものをいいます。
ぬかは穀物を精白した時に出る果皮や種皮、胚芽などをいいますが、日本ではぬかというと米ぬかを指すことが多いです。
栄養価は高いですが、そのまま食べることはほとんどありません。
米ぬかはぬか漬けを作る際のぬか床に使用することが多いです。
炒りぬかは米ぬかを焦げ付かないように乾煎りし、水分を飛ばしたものになります。
炒りぬかにすることで発酵しにくくなり、保存期間が生の状態よりも長くなります。
炒りすぎると焦げるので、甘味がなくなったり風味が損なわれたりします。
スーパーマーケット等で販売されているものは日持ちさせるため炒りぬかになっていることが多く、常温で販売されています。
生ぬかとは?
生ぬかは米ぬかのことをいい、炒りぬかと区別するために「生」と付いています。
生ぬかには油分が含まれているので、空気に触れると酸化します。
そのため夏場などは、2~3日もするとすぐに傷んでしまいます。
生ぬかはぬか床に使用されており、大根やキュウリ、ナスといった野菜を漬けてぬか漬けにすることが多いです。
様々な野菜を使ったぬか漬けがあり、肉や魚、卵、チーズなどを使ったぬか漬けなどもあります。
炒りぬかと生ぬかの違い
炒りぬかも生ぬかも米ぬかであることは共通しており、炒りぬかは米ぬかを炒って水分を飛ばしてあるものをいいます。
生ぬかには油分が多いので傷みやすく、炒りぬかは生ぬかよりも保存性が良くなっています。
そのためスーパーマーケット等で販売されているのは炒りぬかで、生ぬかは販売されていません。
生ぬかは、米屋や農家などで手に入れることができる場合もあります。
まとめ
生ぬかを炒って水分を飛ばしたのが炒りぬかです。
生ぬかよりも炒りぬかの方が保存性が良く、スーパーマーケット等で販売されています。
生ぬかは傷みやすいという特徴があります。