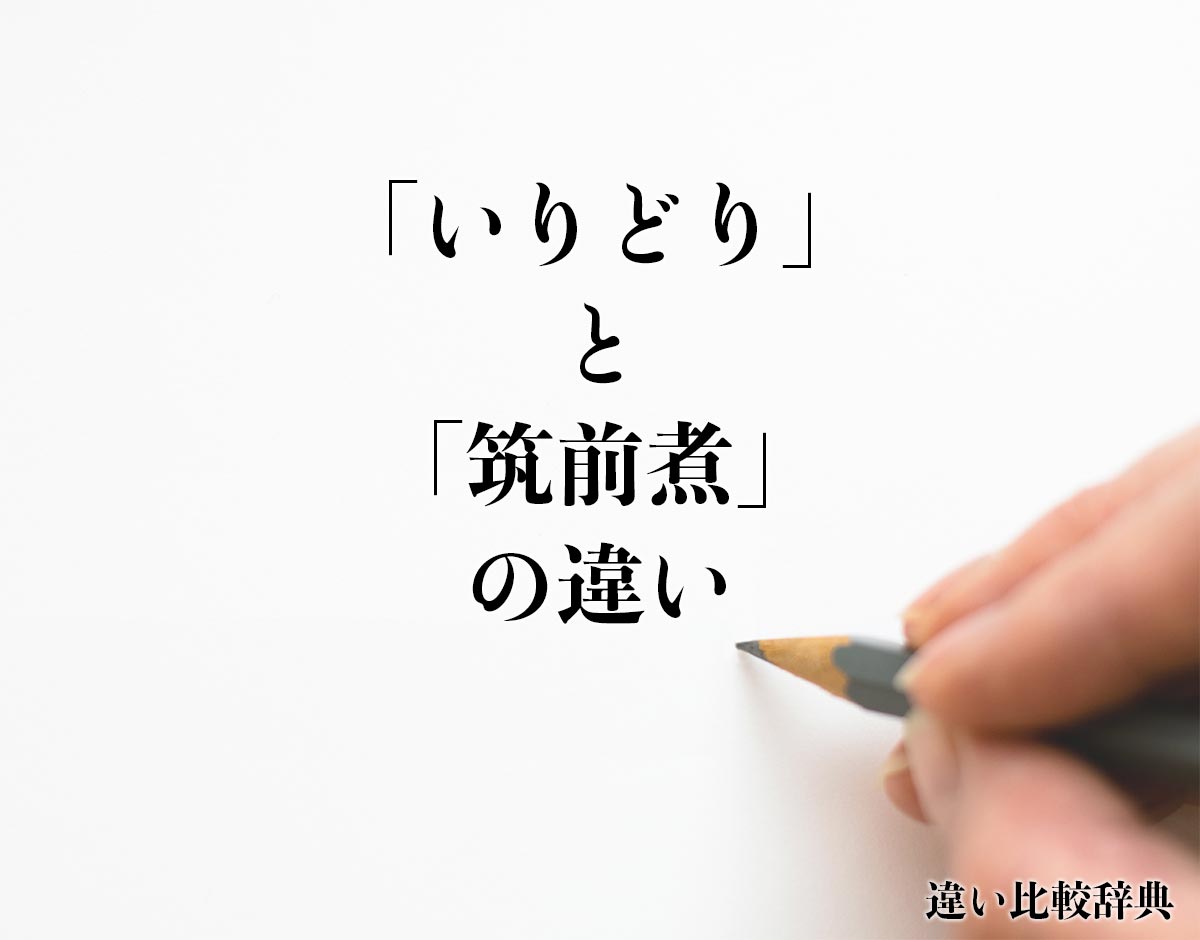この記事では、「いりどり」と「筑前煮」の違いについて紹介します。
いりどりとは?
いりどりとは、鶏肉や野菜などの具材を油で炒めだし汁や砂糖、しょうゆ、みりん等の調味料で味付けした煮物のことをいいます。
漢字では「炒り鶏」と書きます。
最初に油で鶏肉を炒りつけて煮ることから炒り鶏(いりどり)という名前になりました。
家庭料理として知られ、学校給食などで提供されることもあります。
使用する具材は家庭によって違いますが、鶏肉の他にはニンジンやレンコン、ゴボウなどの根菜類を使うことが多いです。
それから干しシイタケやこんにゃく、タケノコ等を使うこともあります。
鶏肉には骨付き肉を使うこともあるようです。
筑前煮とは?
筑前煮とは、福岡県の北部に位置する筑前地方の郷土料理の1つです。
鶏肉や野菜、こんにゃく等の具材を油で炒めてから甘辛く味付けした煮物で、いりどりと同じものを指しています。
また、「がめ煮」や「筑前炊き」と呼ばれることもあります。
筑前煮という名前は、筑前地方以外で使われていた呼び名になります。
油で炒めてから煮るという調理法はそれまでにはなく珍しかったので、筑前地方独特の料理として広まりました。
そのため筑前煮と呼ばれるようになったのです。
油で炒めることでコクが出たり、あくが出にくくなったりします。
いりどりと筑前煮の違い
いりどりと筑前煮は、どちらも鶏肉や野菜、こんにゃく等の具材を油で炒めてから煮る料理のことをいい違いはありません。
筑前煮は福岡の郷土料理として知られていますが、炒り鶏やがめ煮、筑前炊きなど色々な呼び名があります。
ただし、炒める時にしっかりと水分を飛ばしたものをいりどりと呼び、水分を残して煮たのが筑前煮として区別することもあります。
まとめ
いりどりと筑前煮はどちらも鶏肉や野菜を炒めてから煮た料理のことをいい、違いはありません。
筑前煮は福岡の筑前地方の郷土料理として広く知られています。