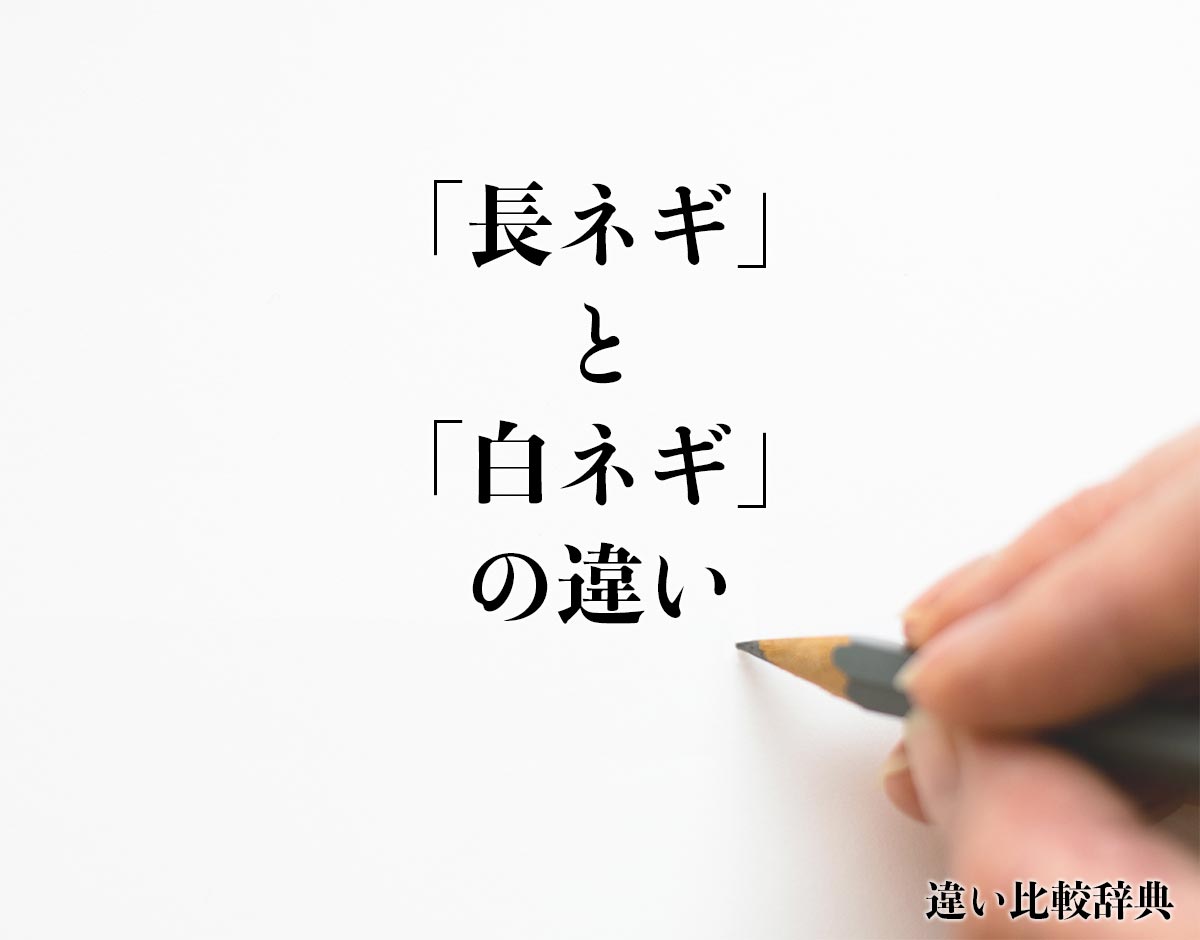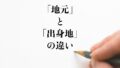お鍋に欠かせない具材の一つにネギがありますが、長ネギといったり白ネギといったりします。
長ネギと白ネギの違いについて紹介します。
長ネギとは?
長ネギとは細長くのびるネギで、主に白い部分を食べる野菜のことをいいます。
根深ネギと呼ばれることもあります。
ネギには大きく分けると2種類あり、長ネギと青ネギになります。
青ネギは全体が緑色の葉で、葉ネギとか万能ネギということもあります。
長ネギは主に関東地方で生産されており、青ネギは関西地方で生産されています。
現在はどちらも全国に流通しているので、関東にいても関西にいても手軽に手に入れることができます。
それから長ネギには、寒さに強いという特徴があります。
秋から冬が旬で、寒さが厳しいほど甘くなります。
鍋物に使われることが多いですが、炒め物や煮物、和え物、天ぷら等幅広い料理に使われています。
中華料理や洋食などにも使われる食材です。
また、長ネギは生で食べることができますが、辛味があります。
辛味の元は硫化アリルという成分で、胃液の分泌を促す働きがあります。
小口切りやみじん切りにして、薬味として使ったりもします。
その他にもビタミンCやカロテン、カルシウム、ビタミンKといった栄養素も含まれています。
長ネギは淡色野菜に分類されますが、青ネギは緑黄色野菜になります。
白ネギとは?
白ネギは根深ネギのことをいい、長ネギと全く同じ野菜です。
地域によって呼び方が異なっています。
白い部分を食用とすることから白ネギと呼ばれるようになりました。
白ネギの代表的な品種には、深谷ねぎ、下仁田ネギ、千住葱、越谷ねぎ等があります。
青ネギの代表的な品種は、京都の伝統野菜として有名な九条葱です。
白ネギは栽培する時に土寄せを行い、根本を光に当てないようにします。
そのため根本が白くなるのです。
白ネギは根深ネギといわれることもあるように、根を深く張っていく野菜です。
関東平野の土壌に適しており、土の中にある部分は白くなります。
それに対して関西地方の土壌は花こう岩質のため、根は張りにくいのです。
青ネギは根を深く張る必要がないため、花こう岩質の土壌でも育ちやすいといえます。
また、白ネギの栽培が盛んな関東平野では強い風が吹きます。
そこで、青ネギを栽培したとすると風で倒されてしまいます。
そういったこともあり、白ネギは関東を中心に栽培が盛んに行われているのです。
長ネギと白ネギの違い
長ネギと白ネギに違いはありません。
根深ネギといわれることもある細長いネギのことをいい、白い部分を食用とするものです。
地域によって長ネギと呼ぶ場合もありますし、白ネギと呼ぶ場合もあります。
どちらも一般的に広まっている呼び名なので、長ネギといっても白ネギといっても大丈夫です。
関東では主に長ネギと呼んでいます。
まとめ
長ネギと白ネギは同じ野菜で、呼び方が違うだけです。
関東では長ネギということが多くなっています。