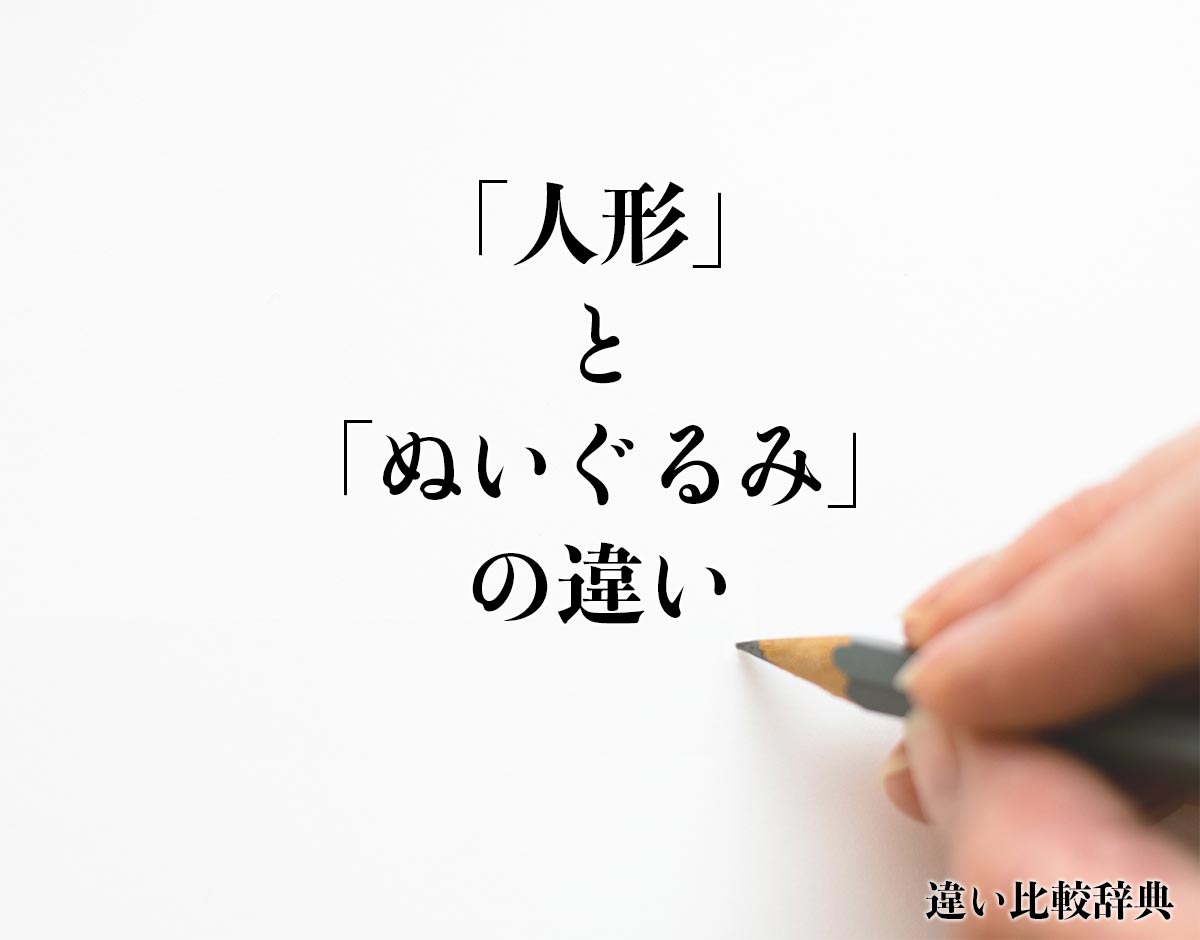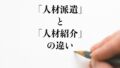この記事では、「人形」と「ぬいぐるみ」の違いについて紹介します。
人形とは?
人形とは、人の形に似せて作った物のことをいいます。
元々は信仰の対象として作られていましたが、子どもの遊び道具として用いられるようになりました。
その歴史は古く、紀元前2000年頃のエジプト王朝時代には存在していたといいます。
現在でも、宗教的な行事に用いられる人形もあります。
日本の伝統的な人形としてひな人形がありますが、これは災いを避けてくれる守り雛として祀られるようになったものです。
昔は子どもの死亡率が高かったため、大人になる前に亡くなってしまう子どもも多かったといいます。
そこで子どもに降りかかる災いを代わりに引き受けてくれるのがひな人形だったのです。
子どもには健やかに成長してほしいという親の願いが込められています。
現在、人形には様々な種類があり、子どもが遊ぶおもちゃの人形もあれば観賞用として精巧に作られているものもあります。
バービー人形やリカちゃん人形は、おままごとや着せ替えを楽しむためのファッションドールです。
子ども向けの人形ですが、大人にもファンが多くコレクターもいます。
ぬいぐるみとは?
ぬいぐるみとは、芯にするものを布で包んで縫い合わせたおもちゃのことをいいます。
動物やキャラクターなどを模しており、漢字では「縫い包み」と書きます。
片手で持てる小さいものから人間と同じ大きさがある大きなものまで色々あります。
ぬいぐるみで有名なのはテディベアで、ドイツのマルガレーテ・シュタイフという会社が世界で初めて販売を行いました。
テディベアはくまのぬいぐるみで、名前の由来はアメリカの大統領だったセオドア・ルーズベルトといわれています。
テディはセオドアの愛称です。
ぬいぐるみにはリラックス効果があるとされ、子どもの寝かしつけなどに使われることもあります。
人形とぬいぐるみの違い
人形は人の形を模して作られていますが、ぬいぐるみは動物やキャラクターなどを模して作られていることが多いです。
ただし、ぬいぐるみの中には人の形をしているものもあります。
それから人形は歴史が古く、元々は信仰の対象として作られたものでした。
そのため宗教的な儀式に使われるものもあります。
ぬいぐるみの歴史は150年くらいで、1880年にテディベアが販売されたのが最初です。
宗教的な意味合いなどはありません。
人形は人の形をしているため捨てる時に抵抗感を感じる人もおり、人形供養などを行うこともあります。
また、人形に使われる素材は様々で、紙や木、土、プラスチックなど様々です。
ぬいぐるみは基本的に、布を縫い合わせて作ったものをいいます。
まとめ
人形は人の形をしているものをいいます。
それに対してぬいぐるみは動物やキャラクターなどを模していることが多いですが、人の形をしているものもあります。
どちらも子どものおもちゃとして使われていますが、人形には儀式に使われるものや観賞用などもあり用途は幅広いです。