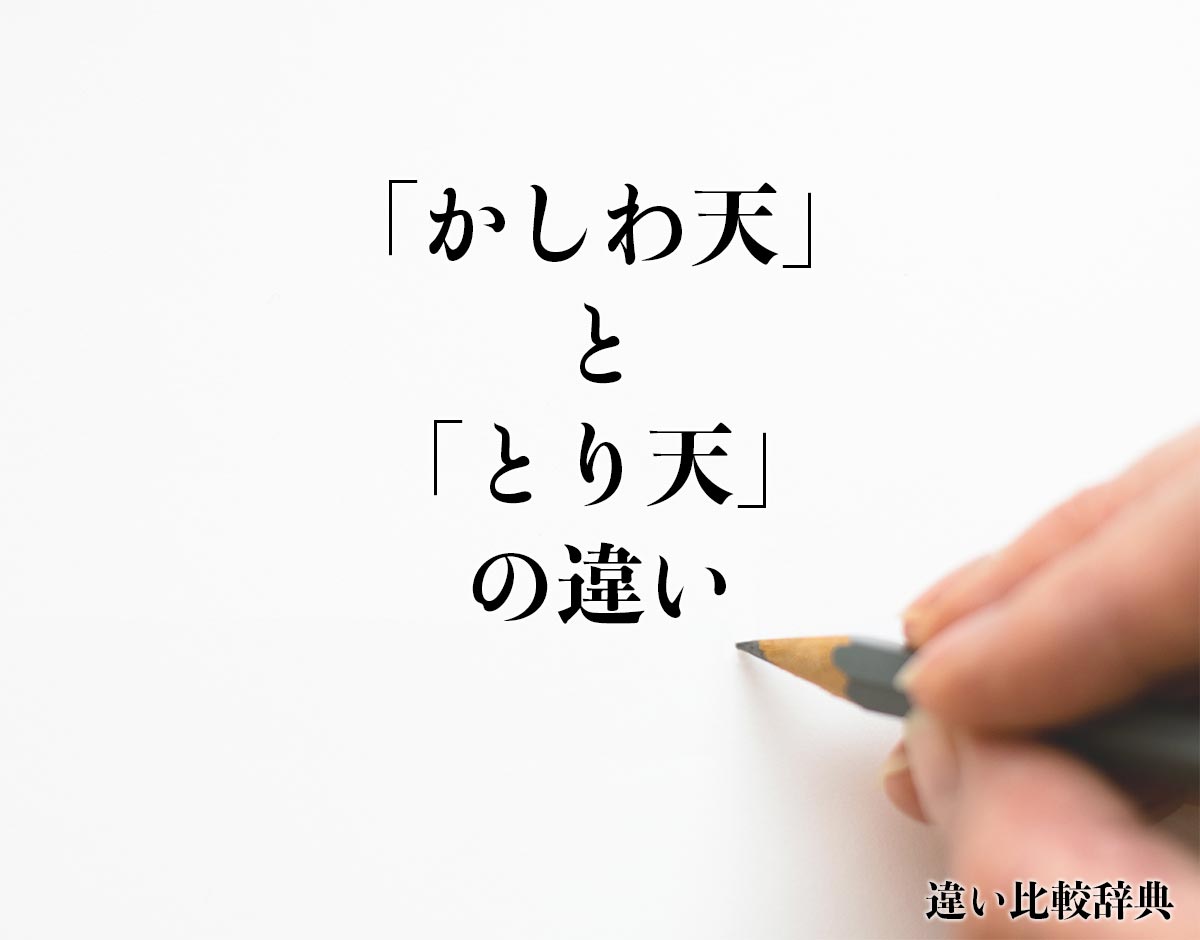かしわ天もとり天も鶏肉を使った天ぷらとしてよく知られています。
かしわ天ととり天にどのような違いがあるのかを紹介します。
かしわ天とは?
かしわ天とは、鶏肉をタレに漬け込んでから衣をつけて揚げた天ぷらのことをいいます。
うどんのトッピングとして人気があり、香川県で誕生したとされます。
今も香川名物としても知られており、讃岐うどんのトッピングの定番です。
なぜかしわ天という名前が付いたのかというと、関西では元々鶏肉のことを「かしわ」と呼ぶことがあったからです。
日本では古来から肉を食べる習慣はあまりありませんでしたが、これは仏教において肉を食べることが禁じられたからという理由があります。
ただし、肉を食べたいと思いこっそり食べる人はいたようで、見つからないように鶏肉のことを「かしわ」と呼ぶようになったといわれています。
かしわ天に使われる鶏肉の部位は決まっておらず、モモ肉やムネ肉、ささみ肉などが使われています。
鶏肉を漬け込むタレは家庭によっても違いますが、醤油やショウガ、お酒などで下味をつけるのが一般的です。
とり天とは?
とり天は、鶏肉に下味をつけてから衣をつけて揚げた大分県の郷土料理です。
昭和初期に大分県にあったレストランが考案した料理といわれています。
天ぷらと同じように小麦粉を卵や水で溶いた衣をつけて揚げますが、厳密には天ぷらとは違う料理です。
天ぷらよりも卵の量が多いのが特徴で、ふわっとした食感になります。
醤油やニンニクなどで下味は付いていますが、ポン酢やタレにつけて食べるのが一般的です。
大分県では家庭でも飲食店でもよく食べられており、定番の定食メニューとなっています。
また、お酒のおつまみとしても人気があり居酒屋などでも提供されます。
大分産のカボスが添えられていることも多いです。
とり天には、モモ肉やムネ肉、ささみ肉などが使われます。
かしわ天ととり天の違い
かしわ天は香川生まれの料理で、うどんのトッピングに用いられることが多いです。
とり天は大分生まれの料理で、ご飯のおかずとして食べられています。
下味が付いていて小麦粉を水や卵で溶いた衣をつけて揚げているのは共通していますが、とり天はタレやポン酢につけて食べることが多いです。
また、大手うどんチェーン店などでは、使用する鶏肉の部位によってかしわ天ととり天を区別していることもあります。
鶏モモ肉を使用しているのがとり天で、鶏ムネ肉を使用しているのがかしわ天としています。
そのため鶏モモ肉の天ぷらがとり天で、鶏ムネ肉の天ぷらがかしわ天だと思っている人も多いです。
しかし、本来はかしわ天もとり天も使用する鶏肉の部位に決まりはありません。
まとめ
かしわ天もとり天も鶏肉に下味をつけ、衣をまとわせて揚げた料理です。
うどんのトッピングとして食べられることが多いのがかしわ天で、ご飯のおかずの定番になっているのがとり天です。
かしわ天の発祥は香川県で、とり天の発祥は大分県です。