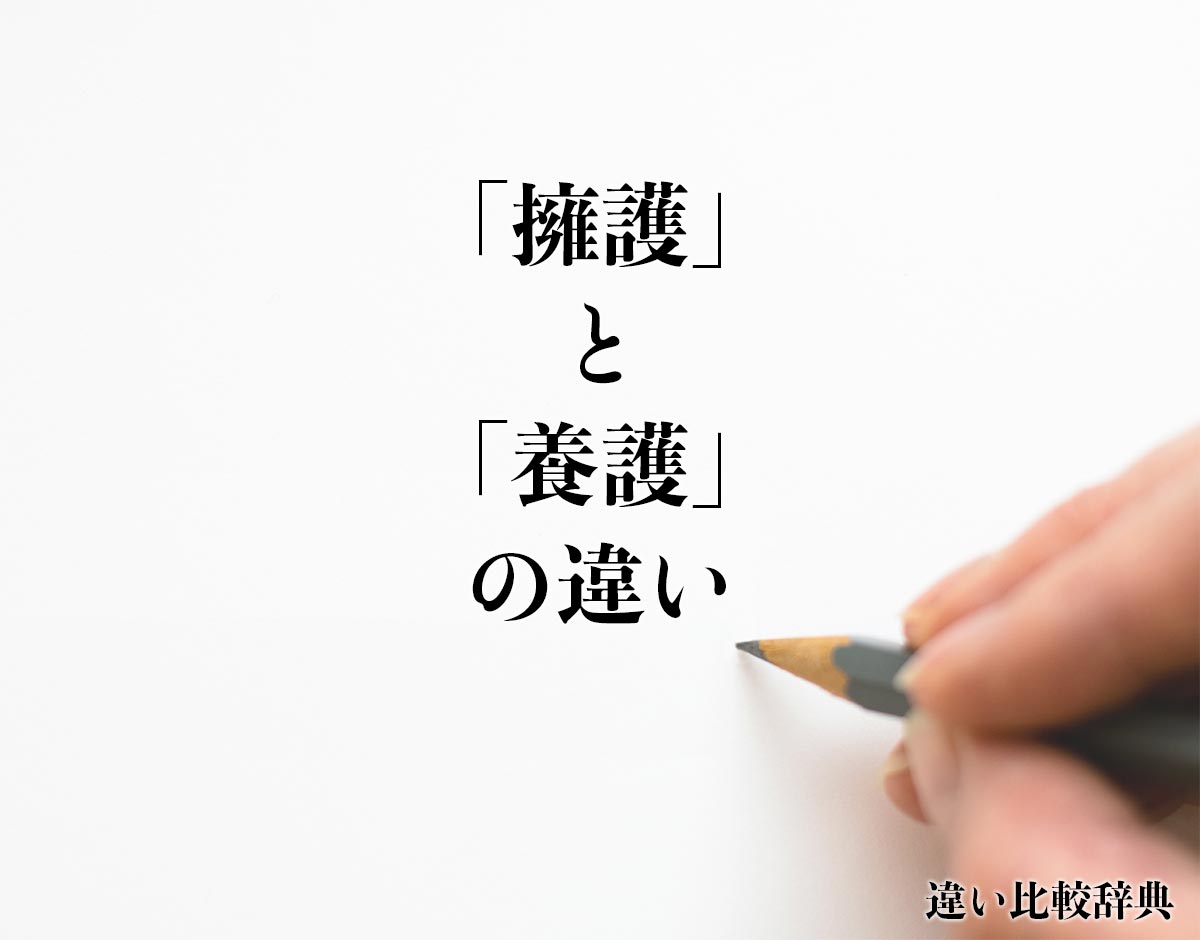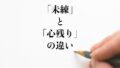この記事では、「擁護」と「養護」の違いや使い方を分かりやすく説明していきます。
「擁護」と「養護」の違い
「擁護」とは、権利や所得をおびやかすことや、身体や生命を奪うような危険なことの影響を受けないように、守ることです。
「養護」には3つの意味があります。
1つめは、衣食を与えるなどして育てて守ることです。
2つめは、児童や生徒の体の状態に気を配り、成長を助けることです。
3つめは、手助けが必要な児童を、特別な施設によって心身両面にわたる能力を伸ばそうとすることです。
どちらの言葉も「ようご」と読みます。
そして、どちらも「守る」という意味が含まれています。
しかし、2つの言葉の意味合いは違います。
「擁護」の場合は、権利や所得を脅かすこと、身体や生命を損なうことから守ることを意味しています。
外からの攻撃から守るようなことです。
主に、口で言うこと、文章にしたことで守ることをいいます。
「養護」の場合は、成長を助けるような意味の守るです。
危険にさらされているから守るという意味ではありません。
「擁護」と「養護」の使い方の違い
前者の言葉は、危険な事柄などの影響を受けないように守ることを指して使用します。
武器で攻撃してきた相手に対して、武器で守ることではなく、言論によって守ることに使うのが一般的です。
後者の言葉は、児童を守り育てることについて使用をします。
「擁護」と「養護」の英語表記の違い
「擁護」は英語で“protection”や“support”と表現をします。
「養護」は英語で“care”や“nursing”と表現をします。
「擁護」の意味
「擁護」とは、権利や所得をおびやかされることや、身体や生命を損なう恐れがあることから、害を受けないように守ることです。
飲食店で注文した料理の中に、異物が入っていたことで考えてみます。
実は、この異物は客が意図的に入れたものです。
この飲食店に迷惑をかけよう、評判を落とそうと考えて、このような行動をしました。
客は店員に「遺物が入っている。
どうしてくれるんだ。
金を返せ」などの言葉を浴びせかけてきます。
店員は謝っていますが、客の怒りは治まりません。
そこにオーナーがやってきました。
オーナーも謝りましたが、異物が入ることは絶対にないと確信していました。
なぜなら、料理に入っていた異物は、この飲食店に存在しないものだったからです。
店員や店が侵害されないように、「このようなものは当店で入るはずがありません」とオーナーは発言しました。
それを見ていた別の客が、「その客が異物を入れるところを見た」といいます。
オーナーや別の客がとった行動が「擁護」です。
言葉によって侵害から守ろうとしています。
このような守る行動を「擁護」といいます。
身体や生命を損なう恐れがあることというと、暴力を受けることを想像することでしょう。
それらから守る手段として暴力を選ぶことはできます。
しかし、「擁護」は暴力に対して暴力で守ることではありません。
主に口から出る言葉や文字に書いたもので守ることをいいます。
「擁護」の使い方
侵害や危害から守ることに使用をします。
侵害とは、権利や所得などを損なう行為をして害を与えることです。
危害とは、身体や生命を傷つけるような危険なことです。
これらから、主に言葉や文章によって守ることを指しています。
「擁護」を使った例文
・『SNSを見た人が擁護してくれた』
・『関係者が○○氏を擁護した』
・『公民権を擁護する』
・『この取り組みを擁護します』
「擁護」の類語
「保護」が類語です。
危険なことから守るという意味があります。
「擁護」の対義語
「侵害」「危害」が対義語です。
「養護」の意味
「養護」には3つの意味があります。
1つめは、食べるものや着るものの面倒を見ながら育て、守ることです。
対象となるのは、自分の世話を自分でできないものです。
主に幼児や児童を指しています。
産まれたばかりの赤ん坊は、自分で食べるものを用意したり、着替えたりすることができません。
そのため、親が食べるものを与え、着るものを与え、世話をします。
こういった行動によって、子どもは不便することがなく、日常生活を送ることができます。
日常生活に不便することがないように、また自立して生活できるように、衣食の面倒をみながら育て、守ることを意味しています。
2つめは、児童や生徒の体の状態に気を配り、成長を助けることです。
小・中・高校には、「養護」の先生という人がいます。
一度はお世話になっているはずです。
この先生の役割は、身体測定のような健康状態を把握するための測定の計画・準備、医師の補助や、保護者向けの配布物の作成、ケガをした生徒の手当てなどです。
「養護」の先生と呼ばれている人が行っていることが、「養護」の意味するものです。
3つめの意味は、手助けが必要な児童を、特別な施設によって心身両面にわたる能力を伸ばそうとすることです。
手助けが必要な児童とは、知的障害を持っていたり、病弱であったり、親がいなかったりするもののことです。
特別な施設とは、そういった児童を主に受け入れているところです。
「養護学校」と呼ばれる学校があります。
知的障害・病弱児・肢体不自由児などを対象とした学校です。
小・中・高校の授業に準じた内容の教育を行うことや、また障害にうちかち生活できるように知識を与えたり、訓練をしたりすることを目的としています。
この学校が行っているようなことが「養護」です。
「養護」の使い方
児童を守り育てることを指して使用します。
「養護○○」という言葉で使用されることが多いです。
「養護」を使った例文
・『養護を必要とすると判断された』
・『養護教諭を対象とした調査』
・『養護されている』
・『養護施設で生活をする』
「養護」の類語
「看護」「看病」が類語です。
病気やケガのあるものを世話するという意味です。
「養護」の対義語
ありません。
まとめ
「ようご」と同じ読みですが、2つの言葉の意味は違います。
一方は侵害などから守ること、もう一方は児童を守り育てることという意味を持っています。