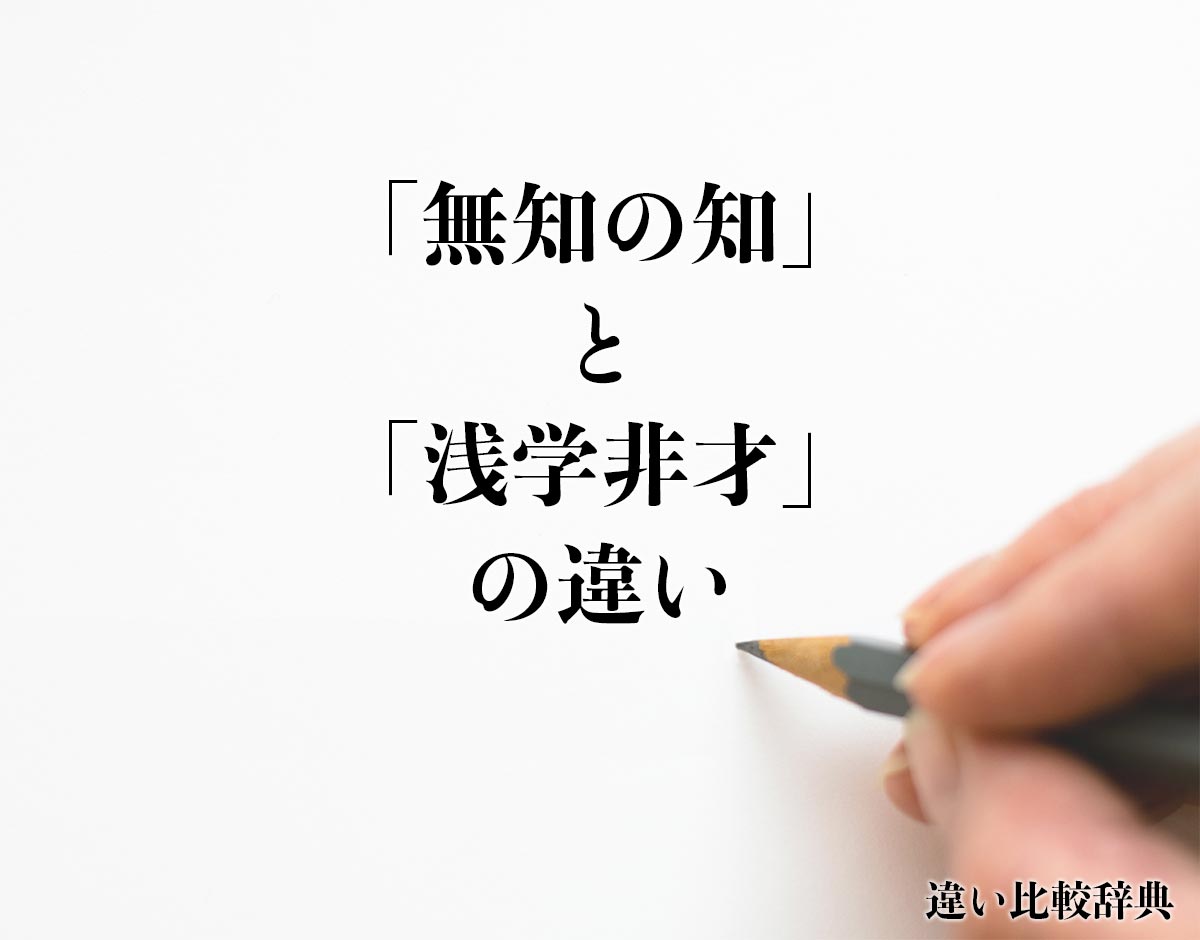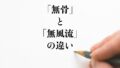この記事では、「無知の知」と「浅学非才」の意味や違いを分かりやすく説明していきます。
「無知の知」とは?
本当は知識がほとんどない無能な人間であることを己で知れというソクラテスの論を「無知の知」【むちのち】といいます。
人前ではあたかも知っていると豪語しても、実際には理解できていないは、聞かれても意味が答えられない人を指す言葉です。
主に、自分が知らないことの方が罪の深さがあるという意味合いで使われています。
「浅学非才」とは?
学問が浅く、無知である人を「浅学非才」【せんがくひさい】と呼びます。
知識も身に付いていないは、才能さえないと感じられる無知な人は能力が無く、人間としても駄目と感じられるのです。
このように、無知、無能なため知識がある人には勝てないといった場面でへりくだって自分の識見を伝える言葉です。
元々は「うすい」という意味から粗末と解釈できる菲を使っていたのが、現代では非才となった四文字熟語になります。
「無知の知」と「浅学非才」の違い
「無知の知」と「浅学非才」の違いを、分かりやすく解説します。
自分が無知であることすら理解できていない無能な者を指す言葉が「無知の知」といいます。
もう一方の「浅学非才」は学歴だの才能といったものに無頓着な人間であると相手に伝えるときに使う言葉です。
職場では部下が上司を立てるため、自分にはそれほどの才能がないと謙遜しては低姿勢を見せて就任するときの挨拶として使います。
「無知の知」の例文
・『何でも知っていると豪語する友人ほど無知の知である』
・『無知の知を頭に入れて勉強した姉が進学校に一発合格した』
「浅学非才」の例文
・『浅学非才な姉でも、科学者としての実力は誰もが認める』
・『実力ある人ほど人前では謙遜して、浅学非才と言う人が多い』
まとめ
四文字熟語には使い方が似ている言葉があります。
ただ、使われている場面に違いがありますので、どう使えばいいか調べてみるといいでしょう。