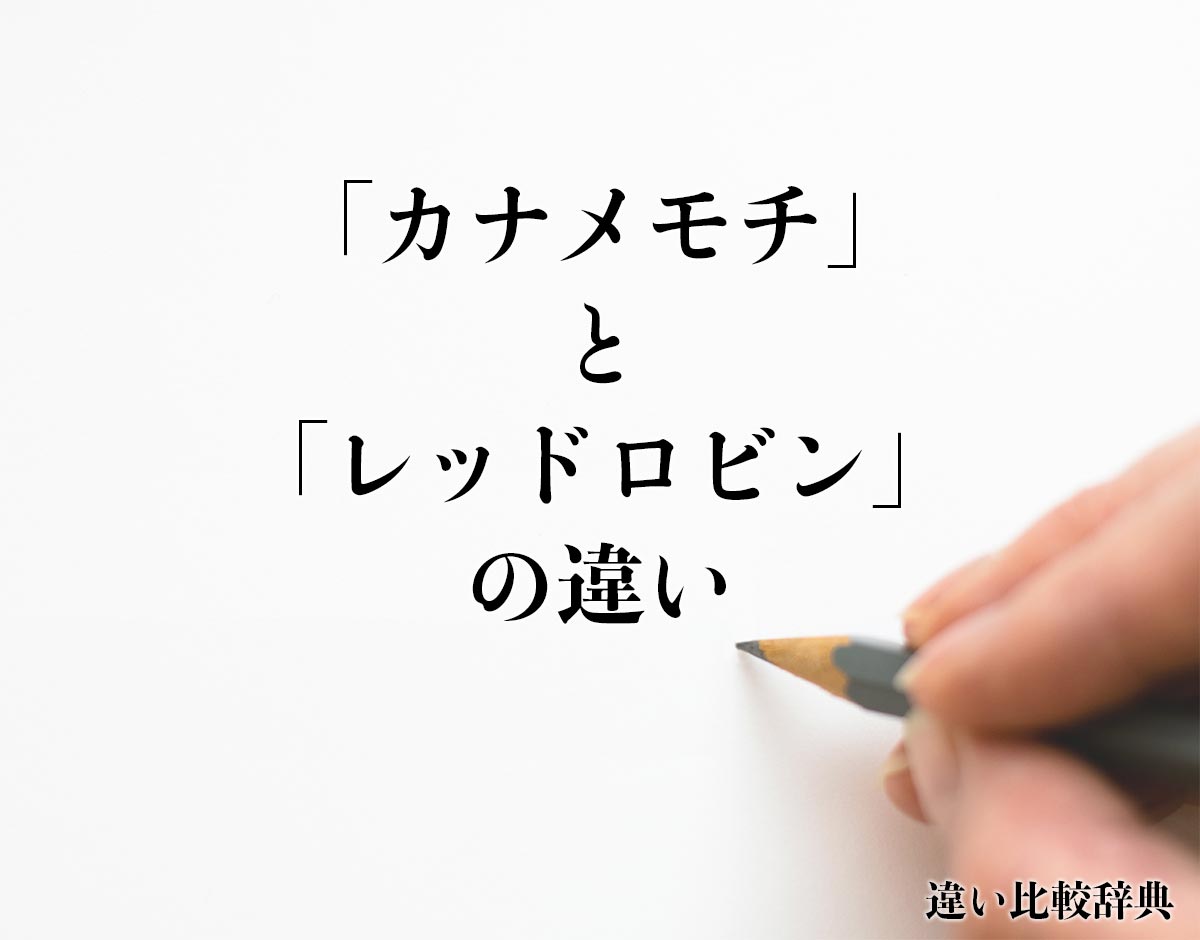この記事では、「カナメモチ」と「レッドロビン」の違いを分かりやすく説明していきます。
「カナメモチ」とは?
カナメモチとはバラ科カナメモチ属に属する常緑広葉樹で、アカメモチやカナメガシ、ソバノキ等と呼ばれることもあります。
カナメモチは本州の東海地方から西の地域と九州、四国に分布しています。
また、中国の南部やタイ、ミャンマーといった東南アジアでも見られます。
カナメモチという名前はモチノキに似ているからですが、モチノキとは全く別の種類に分類されます。
それから扇の要(かなめ)に使われることもあり、カナメモチと名付けられました。
若葉は赤い色をしていて美しく、葉の周囲がギザギザしているのが特徴です。
「レッドロビン」とは?
レッドロビンとはベニカナメモチとオオカナメモチを交配して誕生させた園芸品種で、日本ではセイヨウカナメと呼ばれることもあります。
「red(赤)」という名前が付いている通り、レッドロビンの若葉も鮮やかな赤い色をしています。
成熟すると緑色に変化します。
また、レッドロビンは生け垣の素材としてよく用いられています。
「カナメモチ」と「レッドロビン」の違い
カナメモチもレッドロビンもバラ科カナメモチ属に属しています。
元々、日本に自生していたのがカナメモチで、そこから作られた園芸品種の1つがレッドロビンになります。
カナメモチ属にはそれ以外にも、オオカナメモチやシマカナメモチ、ベニカナメモチ等があります。
カナメモチとレッドロビンの若葉は、どちらも赤い鮮やかな色をしています。
カナメモチの葉には鋸歯(きょし)と呼ばれるギザギザがありますが、レッドロビンにはありません。
そのため葉を見ると区別することができます。
まとめ
レッドロビンはベニカナメモチとオオカナメモチによって誕生した園芸品種です。
カナメモチとレッドロビンの違いは葉にあります。
カナメモチには鋸歯というギザギザがありますが、レッドロビンにはギザギザがありません。