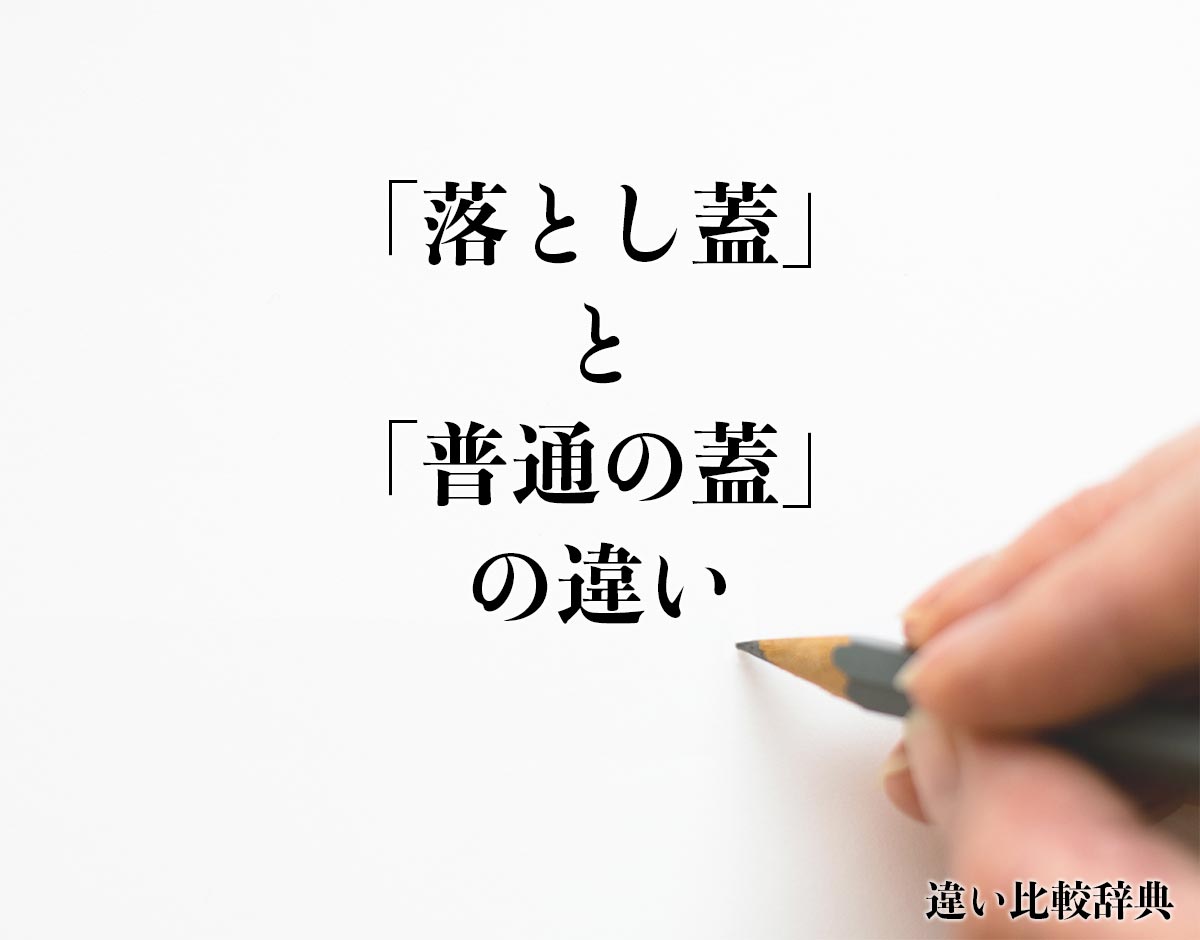この記事では、「落とし蓋」と「普通の蓋」の違いを分かりやすく説明していきます。
「落とし蓋」とは?
鍋で野菜や魚を煮るとき、具材の上にのせる器具を「落とし蓋」【おとしぶた】といいます。
食材の上に直接のせて煮れば、味がよく染み込む効果が得られるのです。
大きさは鍋の口径よりも一回り小さいので、食材に蓋をしたとき隙間が少し開きます。
完全には蓋をするのではなく、隙間を開ければ吹きこぼれません。
この蓋の素材は加熱しても柔軟に対応する丈夫なシリコンゴム製や木の香りが食欲をそそる木製、錆に強いステンレス製といったものが色々揃います。
「普通の蓋」とは?
鍋を買ったときすでに付いているのが「普通の蓋」【ふつうのふた】です。
鍋の口径にぴたりと合うため、中の熱を簡単には逃しません。
火が通り難い食材にも短時間で火を通し、やわからかく煮れます。
素材は中が見えるガラス製や丈夫なアルミ製といったものが多く、片手で持ちやすいのが魅力的な蓋です。
鍋に蓋をすれば熱が逃げず、循環して伝わるため多くの水でもすぐにお湯となり、ガスを節約できます。
また、熱が逃げ難くなるので、分厚いじゃが芋や里芋、肉の中心にもしっかり味が染み込んでいくのです。
「落とし蓋」と「普通の蓋」の違い
「落とし蓋」と「普通の蓋」の違いを、分かりやすく解説します。
煮汁が少なくてもしっかり分厚く切った野菜や魚、肉にも少しの煮汁でしっかり染み込むのが「落とし蓋」です。
魚でも煮崩れを起こし難いのが利点であり、崩れやすい具材にも使えます。
落とすタイミングとしては、材料が煮立ったときや、アクを取ったときです。
蓋をした後は火力を弱火にしてじっくり煮れば、中にしっかり味が染み込みます。
もう一方の「普通の蓋」は鍋と隙間なくぴたりと閉じられるので、中の熱が逃げません。
お湯の吹きこぼれを防ぐには蓋を少しずらすだけです。
「落とし蓋」の方が「普通の蓋」よりも短時間で火を通し、味を染み込ませる効果に優れています。
まとめ
蓋を指す言葉を2つご紹介しましたが、大きさや使い方、素材に違いがあります。
金物屋、ホームセンターなどで手に取り、見比べてみるといいでしょう。