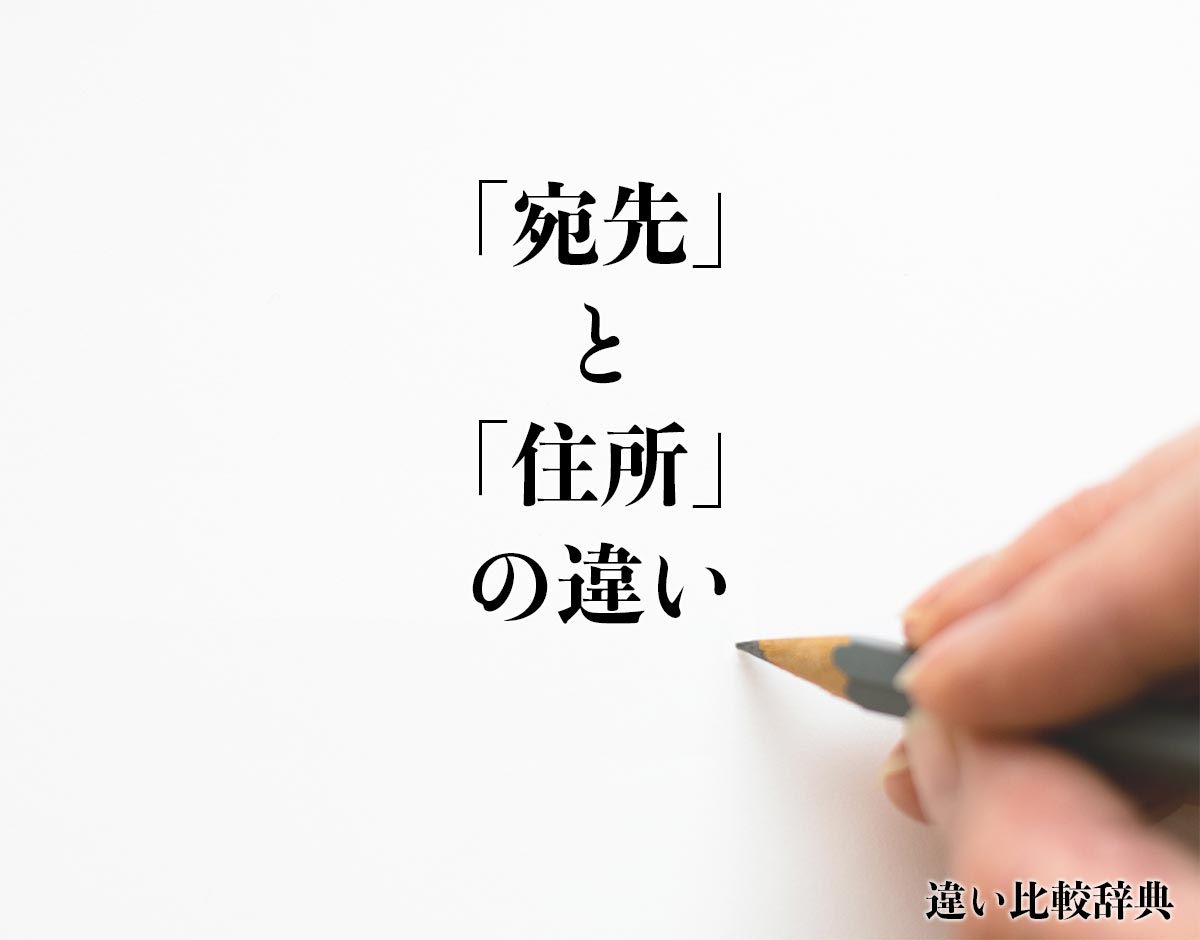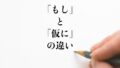この記事では、「宛先」と「住所」の違いや使い方を分かりやすく説明していきます。
「宛先」と「住所」の違い
「宛先」とは、何かを送るとき、そのものを受け取る人やその場所のことです。
「住所」とは、何かの活動をする本拠とする場所です。
Aさんに荷物を送ることで考えてみます。
Aさんに荷物を送るときに宅配便を使う場合は、送り状(伝票)を記入します。
送り状には、「お届け先」と「ご依頼主」という欄があり、荷物を送りたい人はこの部分に記入をします。
「お届け先」というのが「宛先」です。
ここには、東京都○○区など送って欲しい場所を記入し、この東京都○○区などが「住所」になります。
「宛先」は受け取る相手がいる場合をいいます。
お中元、お歳暮、手紙などは受け取る相手がいます。
宅配便を使うときには、受け取る相手がいます。
迷子を警察に連れて行けば、「住所はどこですか」と迷子に対して警察が問いかけることでしょう。
このときの「住所」とは、住んでいる場所のことです。
何かを送り届ける場所、受け取る相手がいる場所のことを指しているのではありません。
住んでいる場所のことを意味しています。
「宛先」と「住所」の使い方の違い
荷物や手紙などを受け取る相手、受け取る場所のことを指して「宛先」を使用します。
何かをする拠点とする場所のことを指して「住所」を使用します。
今私は、○○県○○市に住んでいます。
この○○県○○市のことです。
誰かが何かを送ってくれなくても、「住所」という言葉は使用できます。
「宛先」と「住所」の英語表記の違い
「宛先」は英語で“address”や“addressee”と表現をします。
「住所」は英語で“address”と表現をします。
「宛先」の意味
「宛先」とは、荷物や手紙などを受け取る相手、受け取る場所のことです。
おばあさんに手紙を書いたときのことで考えてみます。
おばあさんに書いた手紙を渡す方法には、自分で直接手渡す、郵便屋さんに届けてもらうという2通りが考えられます。
郵便屋さんに届けてもらうためには、おばあさんがどこに住んでいるのか郵便屋さんに知ってもらわなければなりません。
そうでなければ、手紙をどこに届けたらいいのかわからないでしょう。
おばあさんがどこに住んでいるのか郵便屋さんがわかるように、封筒にはおばあさんが住んでいる場所を記入します。
○○県○○市などです。
そして、自分が住んでいる場所も記入します。
どこに住んでいるのか、おばあさんの分と自分の分の2つを記入していますが、「宛先」とは受け取る相手、この場合はおばあさんが住んでいる場所になります。
懸賞の応募のことで考えてみます。
懸賞の専用はがきには、あらかじめ懸賞を募集しているところの地名やビルの名前、○○係などと記入されています。
おばあさんの手紙の場合と違い、ここに誰かが住んでいるわけではありません。
誰かが生活をしている場所ではありませんが、懸賞の場合だと懸賞の受付をしている人たちが活動している場所になります。
そして、ここでは送られてくるはがきを受け取っています。
こういった、受け取る相手や受け取る場所のことを指している言葉です。
「宛先」の使い方
何かを送って受け取る相手や場所があるときに使用をします。
そもそも、荷物や手紙などを送るのは、誰かに受け取って欲しいからです。
受け取る相手や場所がないときには、この言葉は使用しません。
「宛先」を使った例文
・『宛先を間違えないように注意してください』
・『封筒に宛先を書いて、切手を貼ってください』
・『宛先が記入されていません』
・『宛先を間違えると送ることができません』
・『間違いがないか宛先を確認してください』
「宛先」の類語
「受取先」「受取人住所」などが類語です。
「宛先」の対義語
ありません。
「住所」の意味
「住所」とは、ご飯を食べたり、眠ったりなど、生活するために住んでいる場所のこと、また法人などの場合は、その活動をしている場所のことです。
人間は暮らしていくための家を持っています。
住む場所を転々と変える人も中にはいるでしょうが、一般的には毎日同じ場所で生活をします。
朝起きて、仕事に行って、帰って来て眠るなどをする場所があるはずです。
ここが生活をしている場所であり、家です。
この家がある場所は、○○県○○市などの地名や番号で示すことができます。
その地名や番号のことを意味する言葉です。
組織の場合は拠点としている場所のことを指しています。
この場合は、所在地ともいいます。
どのように表記するのかは国によって違い、日本の場合は都道府県、市区町村群、丁、番地などで示します。
東京都荒川区南千住のような示し方です。
丁や番地は、1の3番地などと表記する場合もあれば、1-3とハイフンを使って表記する場合もあります。
また、マンションの場合は○○マンション100号とすることもあれば、○○マンション100と号を表記しない場合もあります。
「住所」の使い方
生活の拠点となる場所という意味で使用をします。
家を持っていて、そこで暮らしている人なら「住所」を持っていることになります。
賃貸の場合でも「住所」といいます。
法人の場合は、事務所がある場所です。
組織の場合は所在地ともいいます。
日本の場合は、都道府県、市区町村群、丁、番地などで示されます。
「住所」を使った例文
・『引っ越したばかりで住所をまだ覚えていない』
・『住所を教えてください』
・『住所を調べて人を訪ねる』
・『履歴書には必ず住所を記入してください』
・『町が合併されて住所が変わった』
「住所」の類語
「アドレス」「番地」が類語です。
「アドレス」は住んでいる場所、郵便物の宛名という意味があります。
「番地」は、住んでいる場所を示すためにつけられた番号です。
3丁目4番地などがそれです。
「住所」の対義語
ありません。
まとめ
荷物を送るときには、どちらの言葉も使われるので、同じことを指しているように感じますが、正確には同じことを指しているのではありません。
受取先、生活の拠点とする場所という違いがあります。