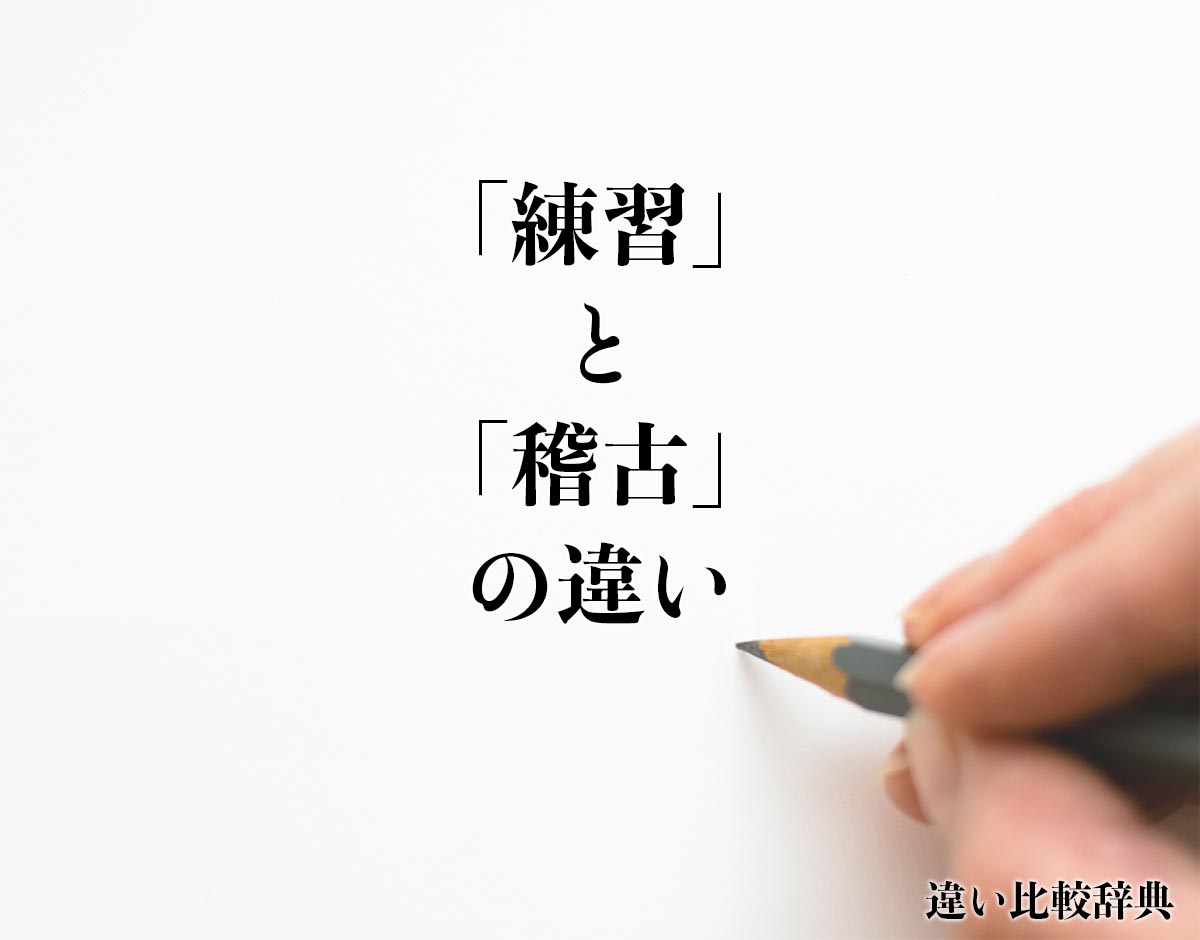この記事では、「練習」と「稽古」の違いや使い方を分かりやすく説明していきます。
「練習」と「稽古」の違い
「練習」とは、技能や学問などを身につけたり、進歩させたりするために、何度も行うことです。
「稽古」には、3つの意味があります。
1つめは、技能・学問・武術などを身につけたり、進歩させたりするために、何度も行うことです。
2つめは、芝居などの本番に向けての練習のことです。
3つめは、昔の書を読んで物の道理や故実を学ぶことです。
技能や学問を身につけたり、進歩させたりするために、何度も行うことという意味は、2つの言葉で共通しています。
2つの言葉が持つ意味に大きな違いはありません。
しかし「稽古」の場合は、身につけたり進歩させたりするための方法が、体系的でなかったり、科学的でなかったりする印象があります。
「稽古」は特に習い事、琴や三味線などの芸事、日本の武術などについていいます。
「練習」と「稽古」の使い方の違い
ほぼ同じ意味なので、同じように使用できます。
たとえば、「毎日練習をする」「毎日稽古をする」など、どちらの言葉を使っても表現できます。
しかし、「稽古」は方法が体系的、科学的でない印象があり、方法が体系的であったり、科学的であったりするものには「練習」という言葉が使用されることの方が多いです。
「稽古」は特に習い事、芸事、日本の武術などを繰り返し習うことについて使用されます。
また、「稽古」は芝居の練習のことを指しても使用されます。
「練習」と「稽古」の英語表記の違い
「練習」は英語で“practice”や“exercise”や“training”と表現をします。
「稽古」は英語で、繰り返し行うことの意味では“practice”や“training”、習い事の意味では“lesson”、芝居などの練習の意味では“rehearsal”と表現をします。
「練習」の意味
「練習」とは、技能や学問を身につけたり、進歩させたりするために、繰り返し行うことです。
英語をうまく話すことができない人が、英語圏の人と英語で会話をできるようにするためには、何度も英語の発音をすることが大切です。
耳で聞く、英語を紙に書くなどだけでは、話す力は身につきません。
そのため、英語を実際に何度も口に出します。
このような行為を「練習」といいます。
プロゴルファーはゴルフトーナメントなどで、素晴らしいプレーを見せてくれます。
ゴルフ未経験者とは違い、よいスコアを出しています。
このようなプレーははじめからできていたのではなく、何度もスイングを行う、何度もパターを打つなどした結果のものです。
何度もスイングをしたりすることを「練習」といいます。
学校などでマラソン大会があるとき、その前から走ることがあると思います。
マラソン大会前から走るのは、走るための体力をつけたり、速く走れるようになったりするためです。
そのために何度も走るという行為を行います。
このような行為も「練習」です。
こういった、技能や学問を身につけたり、進歩させたりするために、何度も行うことを意味する言葉です。
「練習」の使い方
技能や学問を身につけることや進歩させることを目的に、何度も行うことを指して使用をします。
毎日歯磨きをする、毎日顔を洗うなど習慣になっていることではなく、技能や学問の習得・上達を目的に行われるものをいいます。
「練習」を使った例文
・『長距離走の練習をする』
・『毎日練習した甲斐があった』
・『今日は練習を休むことにした』
・『1日2時間ピアノの練習をしています』
「練習」の類語
「稽古」「訓練」が類語です。
「訓練」には、ある事を教えて、何度も行い、自分のものにさせるという意味があります。
体を動かして行うものについていうことが多いです。
「練習」の対義語
対義語はありません。
「稽古」の意味
「稽古」には、3つの意味があります。
1つめは、技能・学問・武術などを身につけたり、進歩させたりするために、何度も行うことです。
日本の茶道には、服装、お菓子の食べ方、茶の飲み方、お茶の点て方など、さまざまな決まり事があり、これらを習得するには時間がかかります。
茶道に関する書籍は数多く販売されていますが、数冊本を読んだだけでは身につきません。
そこで、しっかりと身につけたいと考えたときには、何度も繰り返しお茶を点てる動作をしたり、先生について教えを受けたりします。
このことを「稽古」といいます。
趣味で琴を行っている人もいることでしょう。
琴は弦を箏爪で弾くことで音が出ます。
音を出すこと自体は、琴に始めて触れる人でもそれほど難しくないです。
しかし、曲を演奏するとなると何度も繰り返し琴に触れる必要があります。
曲を演奏できるようにするために、何度も繰り返し行うのです。
このことも「稽古」といいます。
2つめの意味は、芝居などで本番前に行う練習のことです。
芝居を観客に見せるためには、演技などがすっかり出来上がっていなければなりません。
セリフを覚えていない、演技がぎこちないなどでは、観客はがっかりすることでしょう。
観客が満足できる演技をするために、役者は本番前に練習をします。
この本番前の練習のことを「稽古」といいます。
芝居以外でも行われています。
3つめの意味は、昔の書物を読んで物の道理や故実を学ぶことです。
「稽古」の使い方
技能・学問・武術などを身につけたり、進歩させたりすることの意味で使用されることが多いです。
特に日本の武術や習い事についていいます。
日本の武術には、柔術や剣術などがあります。
「稽古」を使った例文
・『○○先生からお茶の稽古を受けている』
・『毎週稽古に通っています』
・『稽古を休んだことがない』
・『上達するために稽古をする』
「稽古」の類語
「練習」「トレーニング」が類語です。
「稽古」の対義語
対義語はありません。
まとめ
技能や学問を身につけたり、進歩させたりするために、何度も行うことを意味する言葉で、2つの言葉の意味はほぼ同じです。
しかし、使われる場面にやや違いがあります。