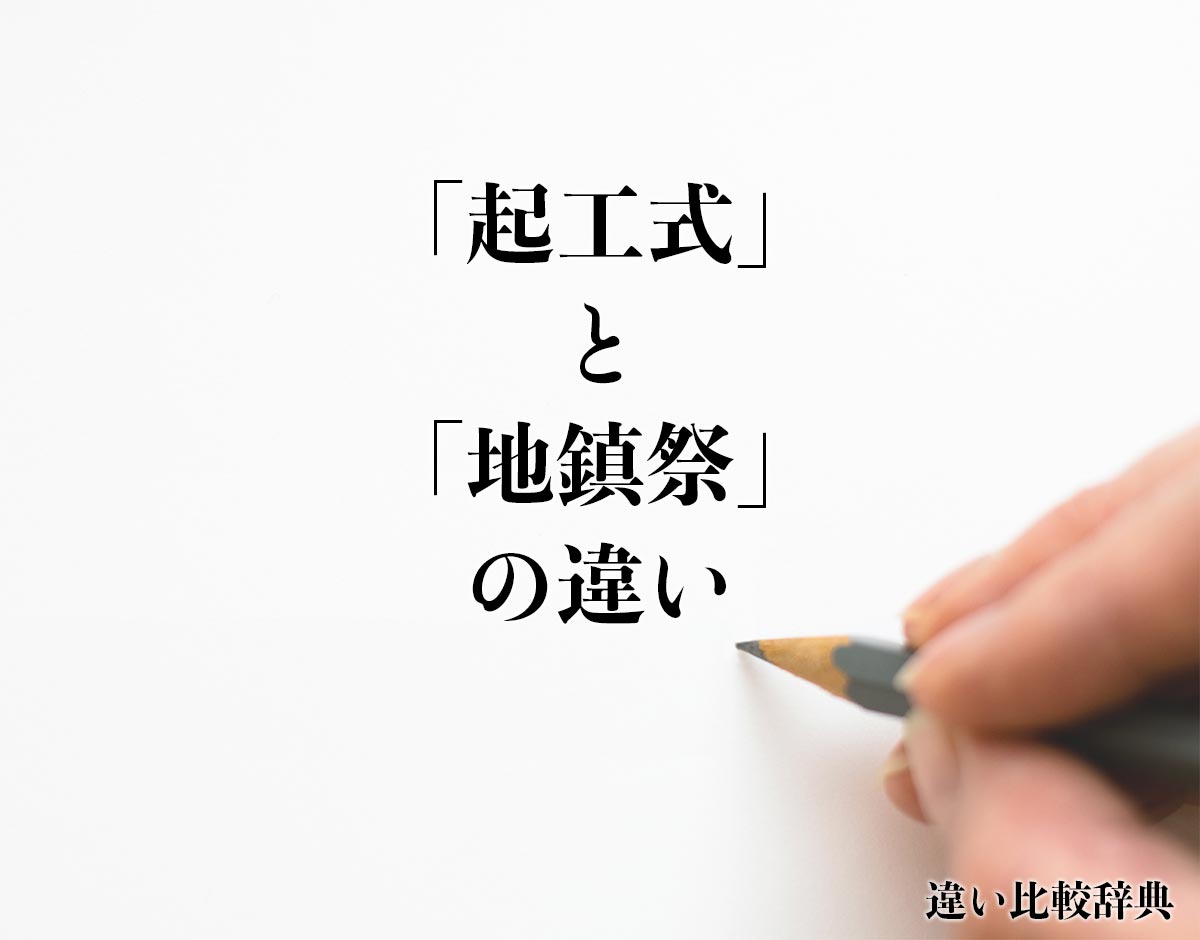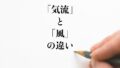この記事では、「起工式」と「地鎮祭」の違いについて紹介します。
起工式とは?
起工式とは、建物の工事を着工する時に行われる式典のことをいいます。
無事に着工まで至ったことを喜び、工事が安全かつ順調に進むことを祈願して行うものです。
神様に工事を始めることを報告する儀式でもあります。
起工式の場合、手置帆負命(たおきほおいのみこと)や彦狭知命(ひこさしりのみこと)、産土大神(うぶすなのおおかみ)を祭神として祀ります。
手置帆負命と彦狭知命は、工匠の守護神です。
産土大神は、その土地の氏神様になります。
公共工事の着工の際には、起工式を行うことが多いです。
地鎮祭とは?
地鎮祭とは建物を建てる際に工事の前に行う儀式で、その土地の氏神様を祀ってそこに建物を建てることを許してもらうために行います。
工事の安全を祈願するもので、安全祈願祭と呼ばれることもあります。
また、土祭りや地祭り、地祝いといったりもします。
地鎮祭では、大地主神(おおとこぬしのかみ)と産土大神(うぶすなのおおかみ)を祀ります。
大地主神は大地の守護神で、産土大神はその土地の氏神様です。
戸建て住宅など個人の建物を建てる場合には、地鎮祭と呼ぶことが多くなっています。
起工式と地鎮祭の違い
起工式も地鎮祭も工事が安全に行われることを祈願する儀式です。
起工式と地鎮祭では、お祀りする神様が違います。
起工式では工匠の守護神である手置帆負命と彦狭知命を祀りますが、地鎮祭では大地の守護神である大地主神を祀ります。
その土地の守護神である産土大神は、起工式でも地鎮祭でもお祀りします。
起工式は工事業者に深く関わるもので、地鎮祭はその土地に今後住む人が深く関わる儀式になります。
公共工事や大規模な建設工事などでは起工式ということが多く、個人の住宅などでは地鎮祭と呼ぶことが多いです。
まとめ
起工式と地鎮祭では、お祀りする神様が違います。
また、公共工事では起工式ということが多く、個人の住宅の工事では地鎮祭ということが多いです。