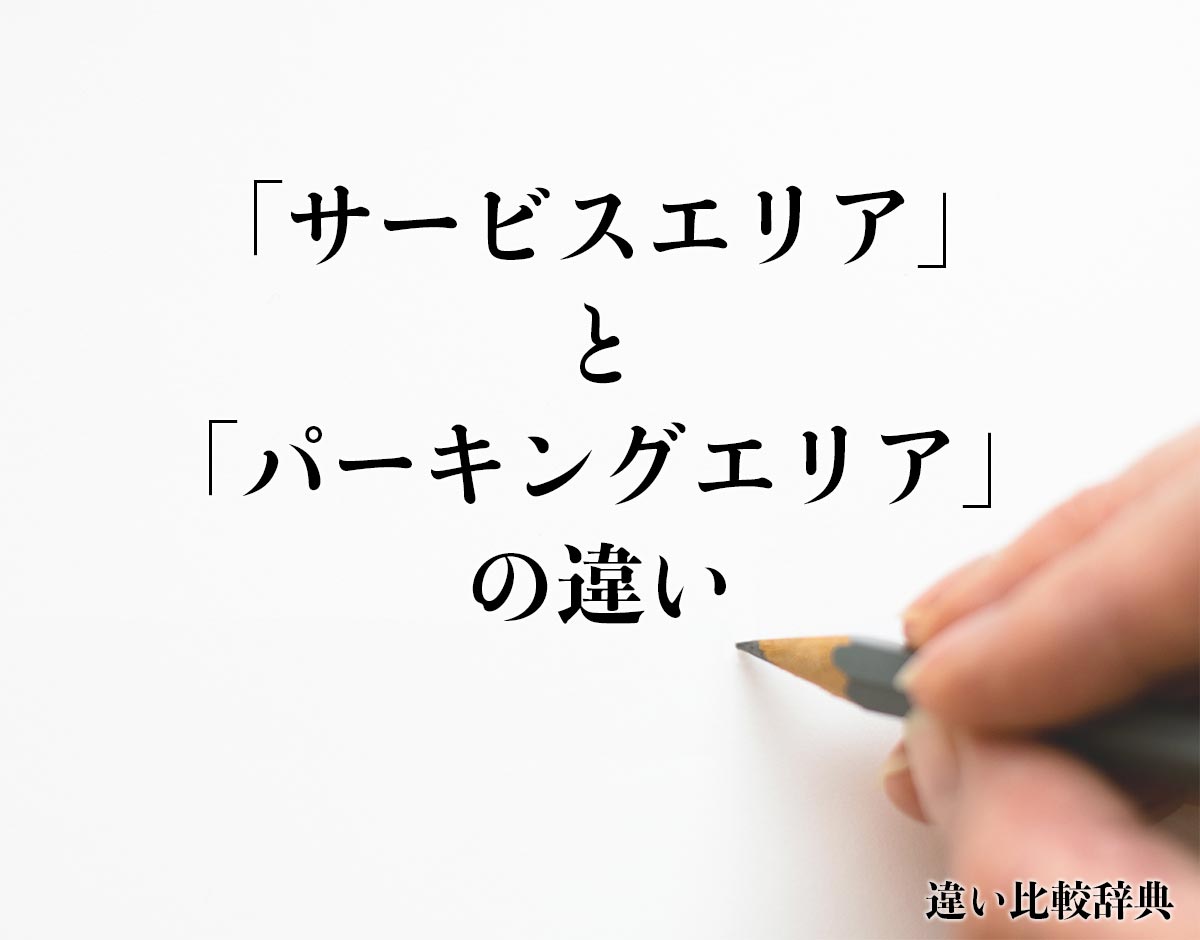2000年代に入り高速道路のパーキングエリアの多様化が進んだ事でサービスエリアの違いをハッキリと明言できる人は少ないと思われます。
この記事では、「サービスエリア」と「パーキングエリア」の違いを分かりやすく説明していきます。
「サービスエリア」とは?
日本では高速道路において基本的に50キロを目安に間隔が置かれて設置されています。
一般的には「パーキングエリア」よりも大規模で多様な施設が展開されている休憩所だと捉えていいでしょう。
主な施設内容としてはドライバーの休憩・食事・自動車のメンテナンス、燃料補給を主眼に置かれたものとなります。
近年では各設置都市の街興しを兼ねて多彩な設備、各自治体の特色を前面に多く打ち出した場所が多く見られるようになりました。
「パーキングエリア」とは?
高速道路や有料道路などで概算15キロ程度の間隔で設置されたものです。
小規模なドライバーの最低限の要求を叶える事ができる休憩施設としての側面が特徴です。
しかし明確な定義はないため、全国に数多くの例外が散見。
近年ではハイウェイオアシス化し巨大化、アミューズメント化した場所も多く見られるようになりました。
「サービスエリア」と「パーキングエリア」の違い
「サービスエリア」と「パーキングエリア」の違いを、分かりやすく解説します。
基本的にはドライバーの最低限の要求を満たせる場所として短い間隔で設置されているのが「パーキングエリア」だと言っていいでしょう。
駐車場、トイレ、自動販売機など必要最小限の設備が設けられており、無人の場所も少なくはありませんでした。
「サービスエリア」はドライバーの休憩はもとより、車のメンテナンス、燃料補給など車用の設備、また情報を入手できる拠点としての役割を果たしてきました。
しかし現在ではこの定義は過去形になりつつあります。
その理由は2005年10月に道路関係四公団が民営化された事で大きく様変わりしていく事になりました。
民営化によりファーストフード・コンビニエンスストアの設置が認められた事により、車の運行量の多い路線の「パーキングエリア」は設備が充実。
なかには「サービスエリア」を越える規模のものも増えてきています。
ハイウェイオアシスが隣接した場所ではこの傾向はさらに如実であり、観覧車やドッグランを設置している場所も増えています。
その反面、この潮流に乗れなかった場所では経営の合理化による無人化の進む場所も増えており二極化しているのが現実です。
まとめ
国土交通省により「サービスエリア」と「パーキングエリア」の違いは提供するサービスの内容、休憩施設相互の位置関係だと定義されていました。
しかし2005年の日本道路公団民営化以降はこの定義が崩れ、両者の差は曖昧なものになりつつあると言っていいでしょう。
チェーン店の出店が認められるなど法規の改正に加えハイウェイオアシスと隣接した「パーキングエリア」ではソフト、ハード両面で「サービスエリア」を凌駕した場所も全国で散見されるようになりました。
現在では「サービスエリア」と「パーキングエリア」を超越した施設化も進んでいます。
新東名高速道路で中日本高速道路が運営しているNEOPASAはその代表例と言っていいでしょう。