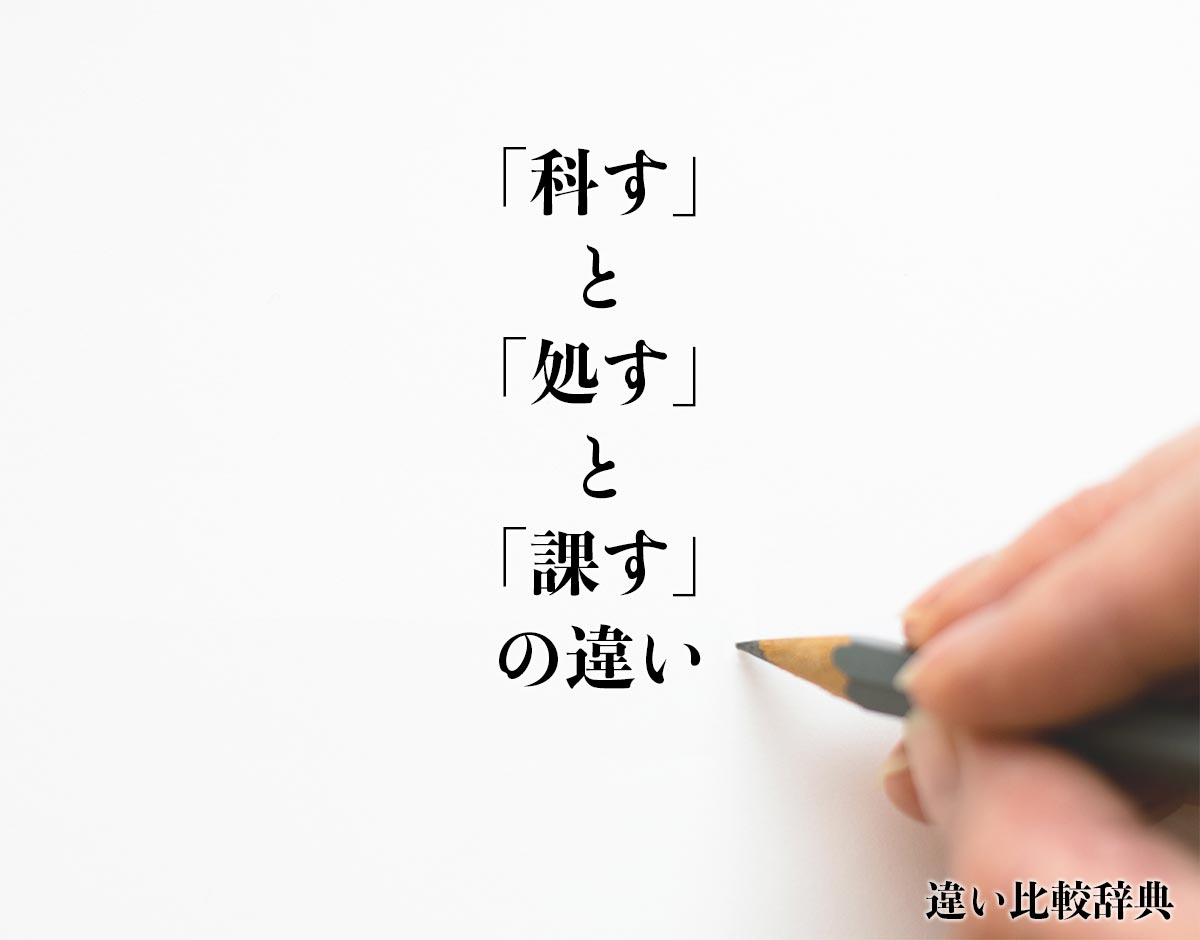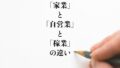この記事では、「科す」と「処す」と「課す」の違いを分かりやすく説明していきます。
紛らわしい言葉を、ひとつずつ学んでいきましょう。
「科す」とは?
科す(かす)とは、ペナルティを与えること。
罰金や違約金を支払わせることです。
悪いことをおこなった人や組織に対して、罰金を言い渡す行為をあらわしています。
反則行為などの罪を犯した人に対して、それ相当のけじめを付けさせる場合に用いています。
そもそも「科す」の「科」には「とがめる」という訳があります。
咎めるとは、何らかの事件を起こした人を問いただすこと。
そのため「科す」でその犯罪に見合う、罰を与えること。
罰金を徴収する行為をさしています。
「処す」とは?
処す(しょす)とは、裁くこと。
それ相応の刑事罰を与えることです。
裁判所が容疑者に対して、懲役10年など具体的な判決をくだすシーンで用いています。
おもに刑事事件の裁判で耳にするのが「処す」です。
もともと「処す」の「処」には「物事を処理する」という訳があります。
そのため検察から上がってきた重大事件を裁いて、具体的な結論をみちびくことが「処す」です。
決着のつかない事件に、ひとつの答えを出すこと。
始末する仕草が「処す」になります。
「課す」とは
課す(かす)とは、負わせること。
対象の人たちに対して、その作業を割り振ることです。
それなりの責任を果たすよう、一方的に言い渡すシーンでつかいます。
やるべき仕事を与えること、義務を負わせることが「課す」です。
もともと「課す」の「課」は、租税から生まれた言葉です。
自治体が税金を徴収する場合に用いていた用語なので、現在でも「課す」というと「罰金を支払わせる」という、お金にまつわる訳があります。
何らかの行為を義務づけること、一方的に与えることが「課す」です。
「科す」と「処す」と「課す」の違い
「科す」と「処す」と「課す」はいずれも「かす」と読みます。
何を負わせるのかによって、選ぶべき漢字が変わってきます。
「科す」はおもに罰金を言い渡す場合につかいます。
そして「処す」は、罪を犯した人に刑事罰を与えること。
懲役刑を言い渡す場合に用いられています。
そして「課す」は、対象の人に何らかの義務を負わせること。
「課す」は「制限を課す」のように犯罪の有無に関わらず、広く利用されています。
まとめるとスポーツ選手や交通違反をした人に罰金を与えるのが「科す」。
罪を犯した容疑者に、判決を言い渡すのが「処す」。
対象となっている人たちに義務やルールを与えるのが「課す」です。
正しく使い分けていきましょう。
まとめ
「科す」と「処す」と「課す」の違いを分かりやすくお伝えしました。
それぞれ「かす」と読みます。
罰金を与えるのが「科す」、懲役刑の判決を下すのが「処す」、義務を負わせるのが「課す」です。
広く用いられているのは「課す」になります。
それぞれの言葉の奥深さを、知っていきましょう。