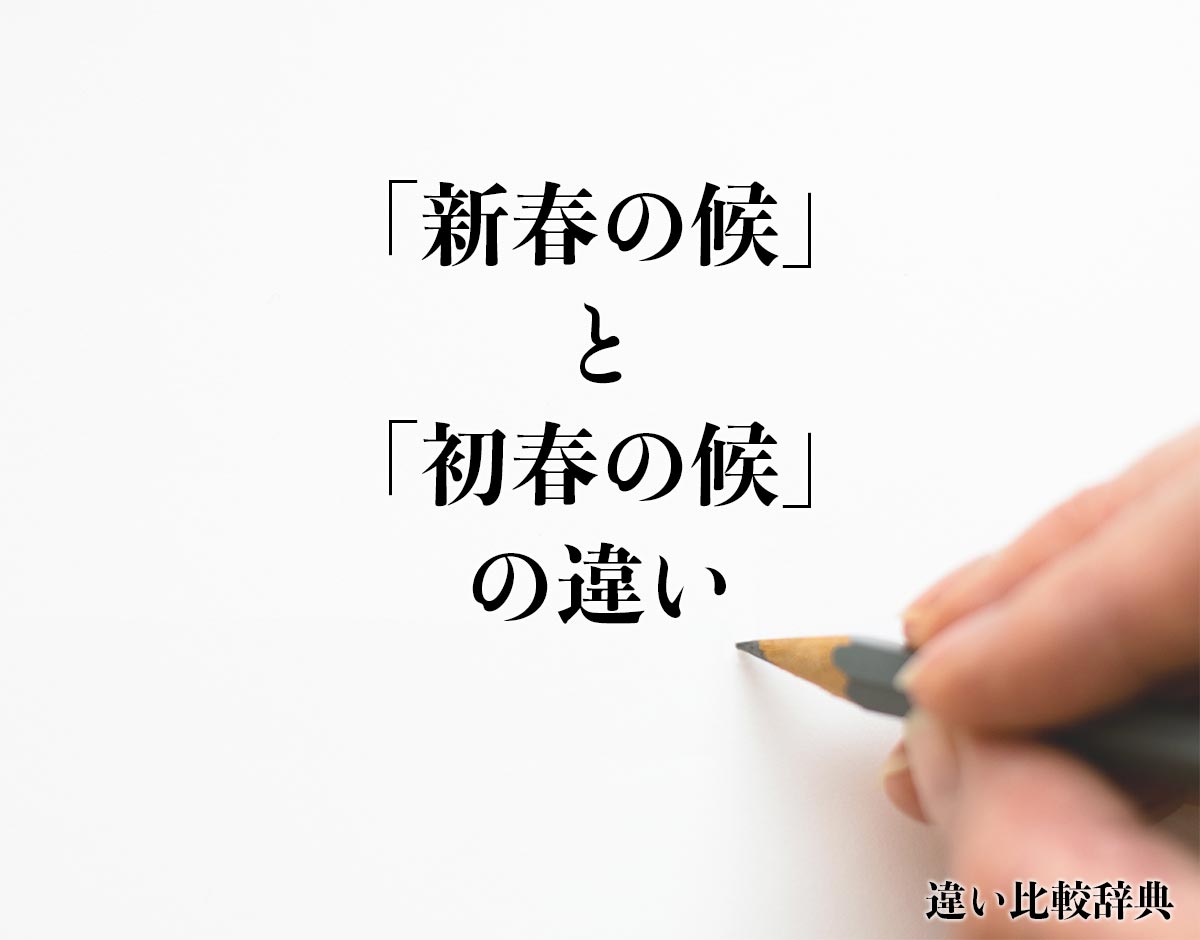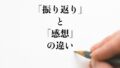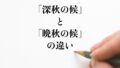この記事では、「新春の候」と「初春の候」の違いを分かりやすく説明していきます。
「新春の候」とは?
新春の候は時候の挨拶の1つで、「新しい年を迎えましたね」という意味があります。
新春はお正月のことで、年賀状などに書くことも多いと思います。
お正月というと季節は春ではなく冬のように思えますが、旧暦では春は1月から始まっていました。
その名残でお正月頃のことを新春と呼んでいるのです。
手紙などで新春の候を使う場合には、松の内までにするのがいいでしょう。
松の内は地域によって異なっており、関東では1月7日までで関西では1月15日までです。
「初春の候」とは?
初春の候も時候の挨拶の1つで、「新しい年を迎えましたね」という意味があります。
初春の候と書いて「しょしゅんのこう」と読みます。
初春はお正月のことで、初春の候は1月1日から1月15日まで使用できます。
お正月は松の内までとされています。
松の内はお正月の事始めから神様が帰られるまでの間で、玄関に松飾をおく期間になります。
1月7日までの地域と1月15日までの地域があるので、初春の候を使う場合にはその地域の状況に合わせて使用する必要があります。
「新春の候」と「初春の候」の違い
新春の候も初春の候も、お正月の時期に使用する時候の挨拶です。
どちらも「新しい年を迎えましたね」という意味で、違いはありません。
新春も初春もお正月のことを指しています。
「新春の候」の例文
・『新春の候、貴社におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます』
「初春の候」の例文
・『初春の候、貴社におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます』
まとめ
新春の候も初春の候も、お正月の時期に使う時候の挨拶です。
「新しい年を迎えましたね」という意味で、違いはありません。
どちらも1月1日から1月15日まで使える言葉ですが、地域によっては1月7日までのところもあります。