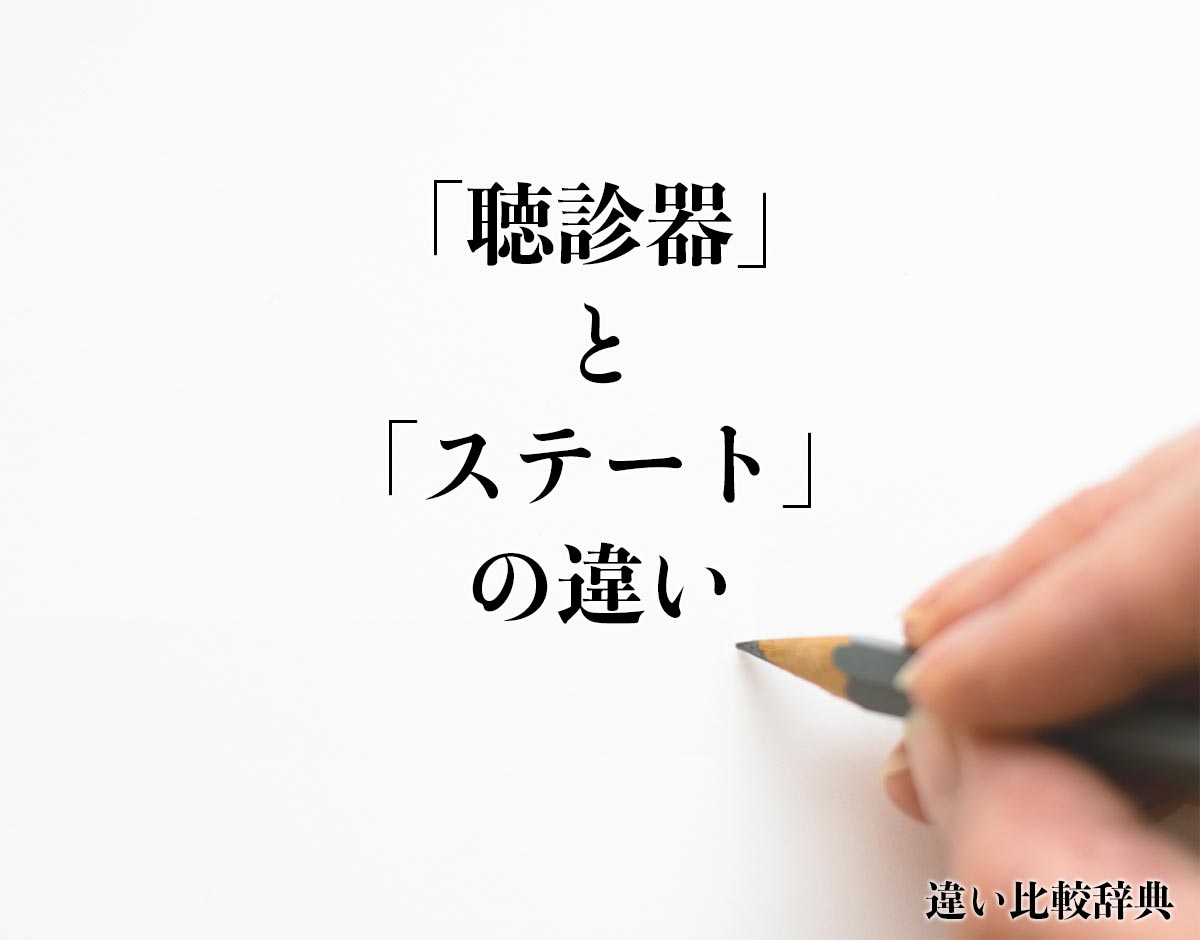この記事では、「聴診器」と「ステート」の違いについて紹介します。
聴診器とは?
聴診器とは、医療の現場で医師や看護師が心臓や肺、血管などの音を聴くために使われる道具のことをいいいます。
聴診器を発明したのは、ルネ・ラエンネックというフランス人医師です。
子どもが木の棒の端を耳に当てている様子を見て思いついたといいます。
それまでは肌に直接耳を当てたり、触れたりして心臓の音を確かめていました。
当時は筒形の木で作られた簡単なものでしたが、改良が重ねられ現在の形になりました。
それに伴い精度も大きく向上しています。
聴診器の仕組みは、肌に触れる部分で音を拾いゴム管を通じて耳に伝えるものです。
肌に当てる部分をチェストピースといいます。
耳に挿入する部分はイヤピースといい、取り外して洗うことが可能です。
看護師が用いるものはナーススコープと呼ばれ、血圧測定の際に血管音を確認する目的で用いられます。
医師が使用するものはドクタースコープと呼ばれ、ナーススコープよりも高い精度があります。
微妙な振動音の違いによって疾患を推察することが求められるからで、価格もドクタースコープの方が高いです。
ステートとは?
ステートとは聴診器のことをいいます。
病院など医療現場では、聴診器ではなくステートと呼ばれることが多いです。
聴診器とステートの違い
聴診器とステートとは同じものです。
聴診器は英語及びフランス語だと「stethoscope」で、発明者であるラエンネック医師が名付けました。
「stetho」には胸という意味があり、「scope」は検査のことです。
日本では医学というとドイツ語が基本だったので、ドイツ語の「Stethoskop」に基づいて「ステト」と呼ばれていました。
それが「ステート」に変化したと考えられます。
まとめ
聴診器とステートは全く同じものなので、違いはありません。
医療現場では聴診器よりもステートと呼ぶことが多いです。