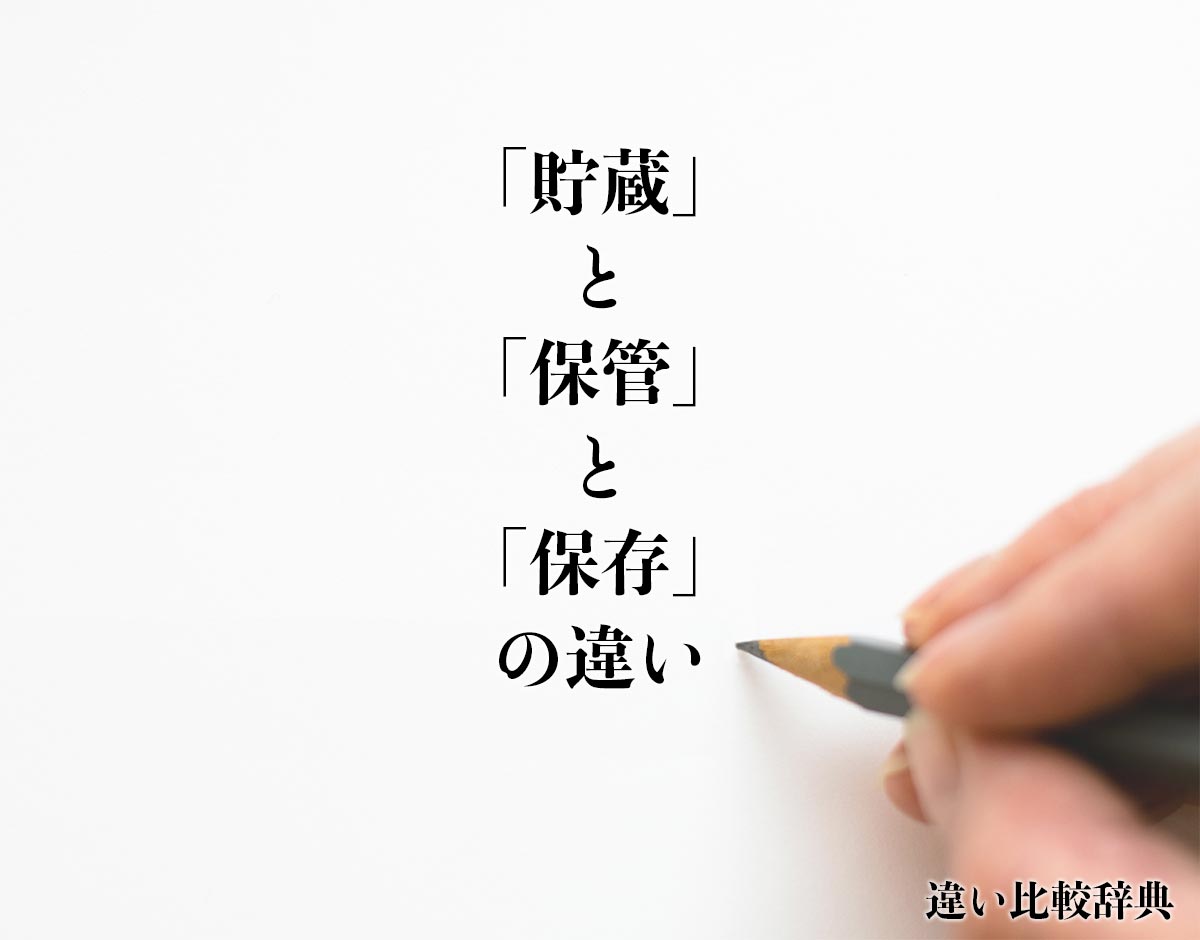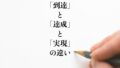この記事では、「貯蔵」と「保管」と「保存」の違いを分かりやすく説明していきます。
紛らわしい三語の差を学んでいきましょう。
「貯蔵」とは?
貯蔵(ちょぞう)とはある物を一定期間、寝かしておくこと。
倉庫や蔵・樽の中に、とめ置いておく様子をあらわしています。
品質が悪くならないように、最高の状態にしておく作業を貯蔵といいます。
「貯蔵」という言葉は「蔵に貯める」と書きます。
蔵とは商品が出荷される前に、一時的に置いておく場所のこと。
安全に管理するために、建てられた建造物をあらわします。
そのためワインや日本酒の貯蔵、ブドウやメロンの貯蔵、水素や天然ガスの貯蔵など、あらゆる商品の蓄えが「貯蔵」と呼ばれています。
「保管」とは?
保管(ほかん)とは、ある物を預かること。
失くさないように、管理しておくことです。
とりあえず預かっておくこと、用事があればいつでも取り出せる状態に備えておく作業を「保管」といいます。
取引先から借りた書類、買ってきたマスク、ガレージにある車などに使われます。
「保管」には「管理する」という訳もあります。
そのためただ預かっているだけではなく、定期的に取り出して不備がないか確認する作業も含まれています。
常に気にかけておき、良い状態にしておく動作が「保管」です。
「保存」とは
保存(ほぞん)とは、取っておくこと。
最新の状態のまま、残しておく作業をあらわします。
保存には「存在を保つ」という意味合いがあります。
こちらが削除しない限り、ずっと維持されているものが保存です。
仕事のシーンで「保存」といえば、パソコン内の文書や画像などを、最新のバージョンで記録することです。
また食品の世界では「冷凍保存」のように、食べられる状態のまま残しておく動作をあらわします。
原状のまま、ずっとキープしておくもの。
長期間にわたって、取っておくものが保存です。
「貯蔵」と「保管」と「保存」の違い
・短いものから保管、貯蔵、保存
「貯蔵」と「保管」と「保存」はいずれも、何かをそこに置いておく動作をあらわします。
捨てずに残しておくことです。
そのうち「保管」は預かっているもの、仮に置いておく物に使います。
そのため一時的な取り置きに使われます。
また「貯蔵」は商品の出荷までに、仮に置いておくという意味合いがあります。
そのため中期的な取り置きが貯蔵です。
そして「保存」は半永久的に残しておくもの、長期的な取り置きにつかわれます。
そのため短いものから保管、貯蔵、保存となります。
残しておく時間にあわせて、使い分けていきましょう。
まとめ
「貯蔵」と「保管」と「保存」の違いを分かりやすくお伝えしました。
いずれも「キープする」という共通の訳があります。
ただニュアンスが少しずつ異なっていて、保管は一時的な仮置きのこと。
貯蔵はそれより少し長い、中期的な貯えをいいます。
長い期間の取り置きが保管です。
言葉を正しく、美しく用いていきましょう。