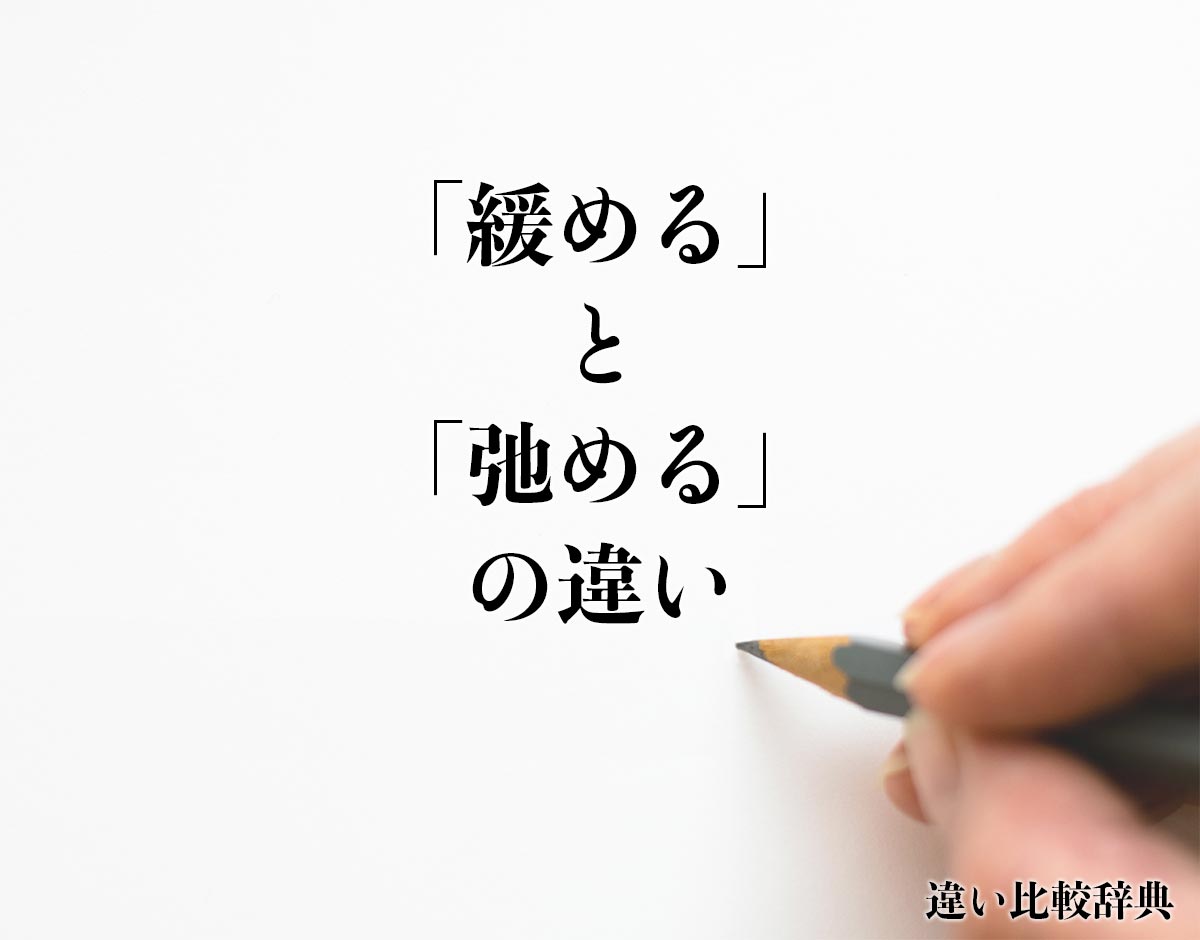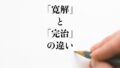この記事では、「緩める」と「弛める」の意味や違いを分かりやすく説明していきます。
「緩める」とは?
腰に巻きつけていた紐の結び目を変えて、きつい状態を改善することを「緩める」【ゆるめる】といいます。
他にも、靴紐を緩めて足が圧迫しないようにする行為を指すわけです。
このように、身体に負担がかかる状態を少しでも良くなるように、ベルトやゴムの幅を広げる行為を意味します。
元々は「糸をゆるめる」という意味がある「緩」を使っているところから、硬すぎる表情を「緩める」という意味で使う場合もある言葉です。
「弛める」とは?
緊張の度合いを緩和する意味で使われているのが「弛める」【ゆるめる】です。
この「弛める」という言葉は常用漢字ではないので、新聞やニュース番組で人々に伝えるときは「緩める」を使うのが一般的です。
元々は「弓のつるがゆるむ」といった意味がある「弛」を使っているところから、ぴんと張ったものがふとした事で「弛む」といった人間の状態を示します。
「緩める」と「弛める」の違い
「緩める」と「弛める」の違いを、分かりやすく解説します。
きつくて辛いと思う状態を改善するために、ベルトや紐の結び目を変える作業を指すのが「緩める」です。
自分が一番楽だと感じる部分に広げて楽にする行為から、それまで張り詰めていた緊張を自ら解きほぐして表情を緩めます。
もう一方の「弛める」は、緊張していた状態から解き放たれて気持ちが明るく、前向きになるといった様を表せる言葉です。
「緩める」の例文
・『基盤作りの作業に集中できないので、廊下に出てベルトを緩めた』
・『真面目な社員も、好きな女性の前では表情を緩めて笑顔になる』
「弛める」の例文
・『きつい靴紐を弛めたおかげで、快適に走れるようになった』
・『かわいらしい鳥の姿に癒されて、ふと表情を弛める』
まとめ
自ら紐の結び目を解いて位置をずらし、きつい状態を緩和するため「緩める」か、緊張を解すために「弛める」といった違いがあると覚えておくといいでしょう。