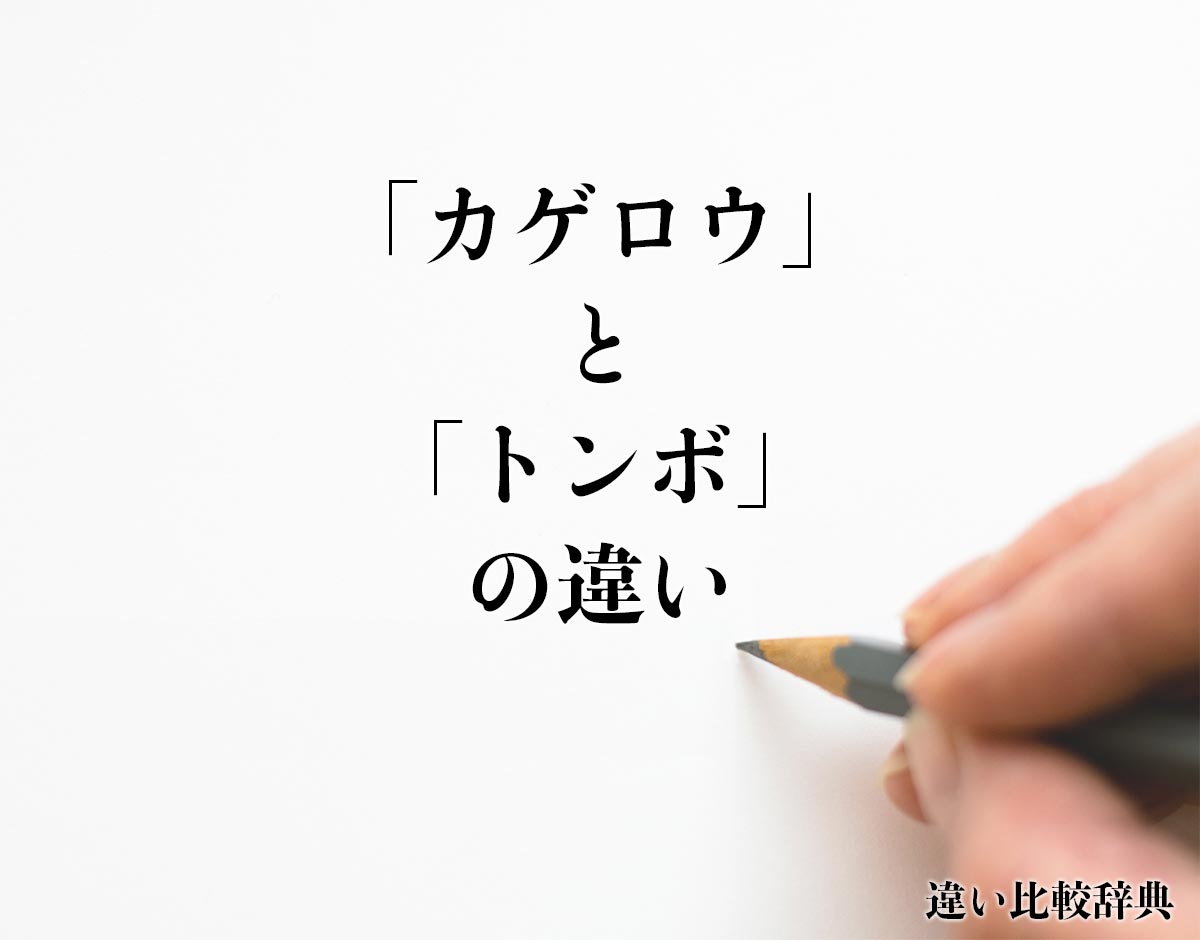子供のころ神社の建物の陰になっている部分にたくさんの小さなすり鉢状の穴があり、そこに「アリジゴク」という小さな虫がいるのを見つけたことがあるでしょう。
これは、「ウスバカゲロウ」という昆虫の幼虫でした。
それでは、この「カゲロウ」とはどういう意味でしょうか。
また、「トンボ」とは、どう違うのでしょうか。
この記事では、「カゲロウ」と「トンボ」の違いを分かりやすく説明していきます。
「カゲロウ」とは?
「カゲロウ」とは、昆虫の一つで「カゲロウ目」に属するもののことを言います。
多くの種類があり、ほとんどは大きな羽を持ちます。
幼虫時代はすべて水の中で過ごし、変態は不完全です。
つまり、蝶のように蛹の形態を経るのではなく、部分的に入れ替わります。
幼虫はすべて水中で過ごすと言った通り、実は前述の「ウスバカゲロウ」は「カゲロウ目」の昆虫ではなく「アミメカゲロウ目」という近縁の種類の昆虫です。
「トンボ」とは?
「トンボ」とは、昆虫の一つで「トンボ目」に属するもののことを言います。
大きな羽と細い胴体を持ち、日本のほとんどの場所で見ることができます。
「カゲロウ」と同様に、「トンボ」も不完全変態の昆虫であり、蛹の状態はありません。
「カゲロウ」と「トンボ」の違い
「カゲロウ」と「トンボ」の違いを、分かりやすく解説します。
この2つは「蜻蛉」という単語を「カゲロウ」とも「トンボ」とも読むように元は区別なく使われていましたが、現代の生物の分類においては全く違う昆虫を指します。
つまり、「カゲロウ」とは昆虫というカテゴリーの中の「カゲロウ目」に分類されるもので、日本だけでも100以上の種類があります。
それに対して「トンボ」は「トンボ目」に分類されるもので、日本では200種類が存在します。
両方とも胴体の両側にやや透明の大きな羽を持つという部分は同じですが、最も大きな違いは「カゲロウ」の胴体が若干太く、種類によってはだんだん細くなって先に刺のようなものがあるという部分です。
それに対して、多くの「トンボ」の胴体は細くて根本と先の太さが変わりません。
まとめ
この記事では、「カゲロウ」と「トンボ」の違いを、解説してきました。
序文で記述したように、「アミメカゲロウ目」の「ウスバカゲロウ」の幼虫は、その名前の通り、主食がアリでした。
やわらかい砂や土にすり鉢状の穴を掘って、その下に潜ってアリが落ちてくるのを待って捕食します。
子供たちは、その習性を利用して、どこかで捕まえてきたアリを、この穴に落として、「アリジゴク」の出現を待っていたものでした。