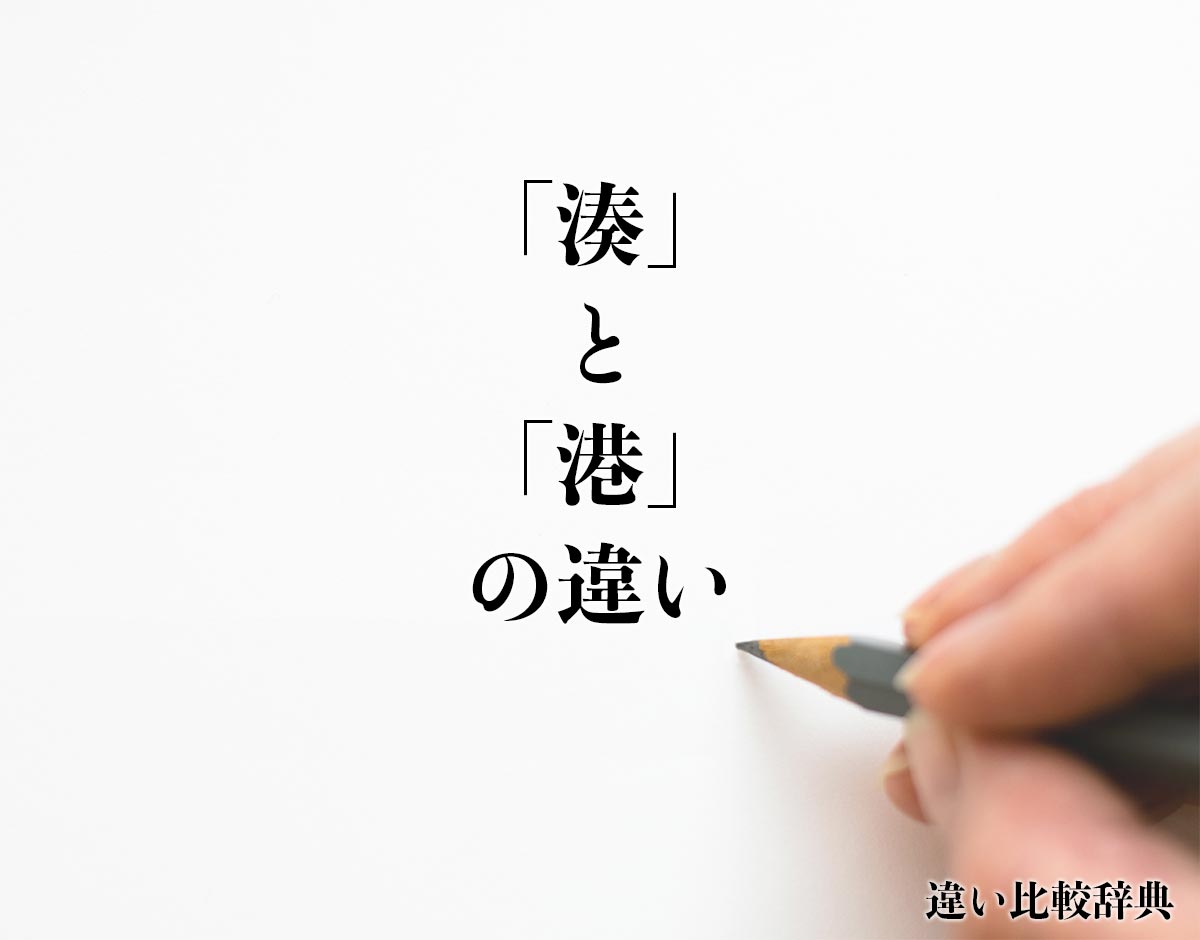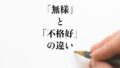この記事では、「湊」と「港」の違いについて紹介します。
「湊」とは?
湊とは、水上交通や漁業を行うための船が集まる場所のことをいいます。
湊は「水の門」を表した漢字で、古事記や日本書紀などには「水門」と書かれています。
「湊」という漢字に使われる「奏」には、「集まる」という意味があります。
さんずいを加えることで、船が集まる場所を表しているのです。
古くは海や川、湖といった水の出入り口や入り江、内湖など地形を表す言葉でした。
それがその地形を利用して作られた港湾のことを指すようになったのです。
「港」とは?
港とは、船舶が安全に停泊したり船舶に乗り降りしたりするところをいいます。
港には幾つか種類があり、漁港や商港、軍港、フェリー港、工業港、マリーナ等があります。
漁港は主に水産物を扱う漁船が停泊します。
商港は貨物船やコンテナ船などが停泊し、外国や国内での貿易に用いられます。
工業港は工業地域にある港で、タンカーや原料輸送船など工業製品を主に取り扱います。
マリーナは、観光やレジャーを目的とする船舶が停泊する港です。
遊覧船やプレジャーボート、ヨット等があります。
港は経済的な発展に伴い港湾都市として整備され、外国との貿易に使われる港には検疫所や出入国管理所、税関なども設けられています。
港がある都市を港町といったりもします。
「湊」と「港」の違い
昔は港湾施設のうち、陸上にある船着き場が「湊」で水路が「港」でした。
そのうち船着き場も「港」に含まれるようになり、現在では「港」を使うことがほとんどになっています。
そのため「湊」というのは古風な印象があり、日常的には使用しません。
昔は「湊」が使われていたので、現在でも地名に「湊」という字が使われているところは全国に存在しています。
まとめ
「湊」は船着き場のことを指す言葉でしたが、現在ではあまり使われなくなりました。
それに代わって使われるようになったのが「港」です。